すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について
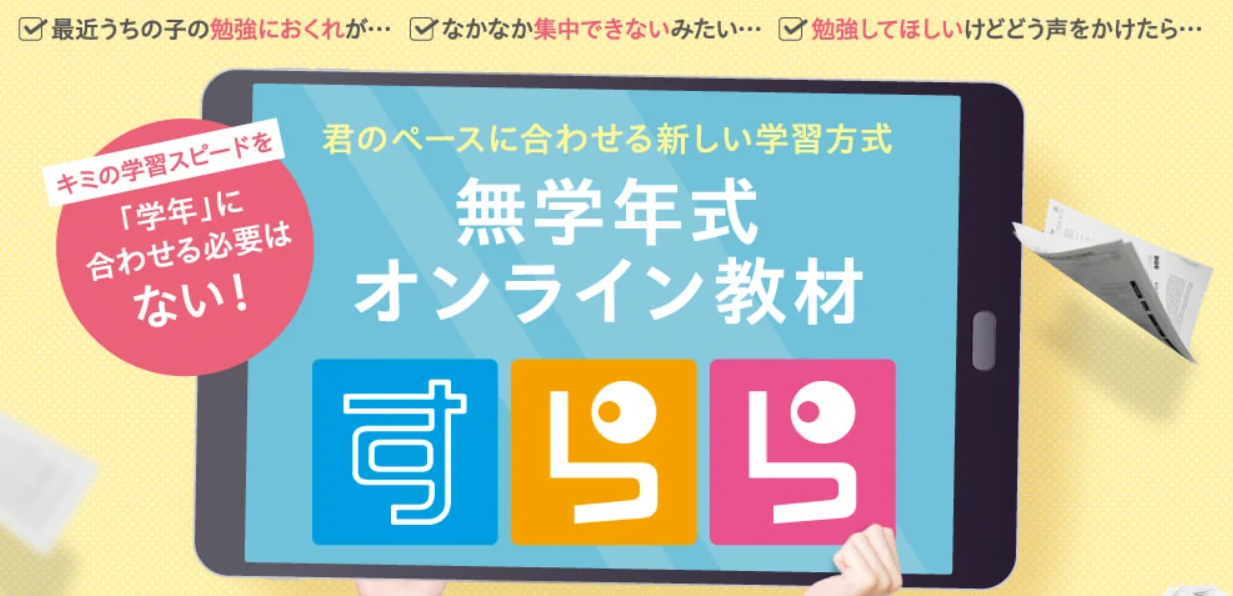
すららは、不登校の子供の学習を支援するオンライン教材のひとつですが、一部の学校や自治体では「出席扱い」として認められることがあります。
不登校の理由はさまざまで、「学校の環境が合わない」「集団生活が苦手」「学習のペースが合わない」といったケースも多くあります。
しかし、出席日数が不足すると進級や卒業に影響する可能性があるため、保護者にとっても大きな不安要素となります。
すららを活用すれば、自宅学習をしながら学校の出席扱いとして認めてもらえる可能性があるため、不登校の子供にとって安心できる選択肢のひとつです。
では、なぜすららが出席扱いになるのか、その理由について詳しく説明します。
理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
すららは、ただのオンライン学習ツールではなく、学習の進捗を客観的に記録し、学校や教育委員会に提出できるレポートを作成できるのが特徴です。
不登校の子供が出席扱いになるためには、「きちんと学習していることを証明する資料」が必要になることが多いですが、すららを活用すれば、この要件を満たしやすくなります。
学習の質が一定のレベルで保たれ、継続的な記録が残るため、学校側にとっても「安心材料」として評価されやすいのです。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
すららでは、学習の進捗や取り組み状況が自動的に記録され、保護者や学校が確認できるようになっています。
これにより、「どの科目をどのくらい学習したのか」「どの単元まで進んでいるのか」といった情報が明確に残ります。
不登校の子供が出席扱いになるためには、学校側に対して「家庭学習をしっかり継続している」ことを証明する必要がありますが、すららの学習レポートを提出することで、学校に対して具体的な学習状況を示すことができるのです。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい
すららは、学習の進捗を自動で記録するため、保護者が毎回手書きで学習記録を作成する必要がありません。
学習履歴やレポートをすららのシステム内で管理できるため、学校側に提出する資料として活用しやすくなっています。
また、学校としても、学習状況が客観的に記録されていることは「継続して学習している証拠」として評価しやすいため、出席扱いとして認められる可能性が高くなるのです。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
すららは、単に「学習できる環境を提供する」だけでなく、子供一人ひとりに合わせた学習計画を立て、継続的にサポートしてくれるシステムになっています。
不登校の子供が出席扱いになるためには、「計画的に学習を進めていること」「継続して学習できていること」が求められる場合がありますが、すららはこの両方を満たす仕組みになっているため、学校側にアピールしやすいのが特徴です。
すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる
すららには「すららコーチ」という専任のサポートスタッフがついており、子供の学習を継続的にサポートしてくれます。
コーチは、子供の特性や学習ペースに合わせた計画を立て、適切なアドバイスを提供してくれるため、無理なく学習を続けることができます。
このように、計画性を持って学習が進められていることを学校側に示せるため、出席扱いの条件を満たしやすくなります。
すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる
不登校の子供にとって、「自分で学習を続ける」のは簡単なことではありません。
しかし、すららでは専任コーチが継続的にサポートしながら、子供に合った学習計画を作成してくれるため、「途中で学習をやめてしまう」「何を学習すればいいかわからない」といった状況になりにくくなっています。
学校側にとっても、学習を計画的に進めていることが明確であれば、出席扱いとして認めやすくなります。
すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる
すららは「無学年式」の学習スタイルを採用しており、学年に関係なく自分のペースで学習を進めることができます。
不登校の期間が長くなってしまうと、「学年相応の学習ができていないのではないか」と学校側が懸念することがありますが、すららでは「必要な単元に戻って復習する」「得意な教科はどんどん先に進める」といった柔軟な学習が可能です。
このように、学習の遅れを取り戻せる環境が整っているため、出席扱いとして認められやすいのです。
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる
不登校の子供が出席扱いとなるためには、家庭だけでなく、学校や学習支援サービスとの連携が重要になります。
すららは、家庭・学校・すららの三者が協力しやすい仕組みを整えているため、保護者が一人で学校対応を行う負担を軽減しながら、スムーズに出席扱いの申請を進めることができます。
特に、必要な書類の準備や、学習の進捗報告のサポートを提供することで、学校側がすららでの学習を理解しやすくなり、出席扱いとして認められる可能性が高まります。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
すららを活用して出席扱いを申請する場合、教育委員会や学校が求める書類を適切に準備することが求められます。
すららでは、どのような書類が必要になるのか、どのように準備を進めればよいのかといった具体的な情報を提供しており、保護者がスムーズに手続きを進められるようサポートしています。
これにより、学校側とのやりとりがスムーズになり、出席扱いの承認が得られやすくなります。
すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる
出席扱いの申請には、学習の記録や成果を示すレポートが必要になりますが、すららでは専任コーチが学習レポートの作成をサポートしてくれます。
すららのシステムには、学習履歴や進捗を記録する機能があり、フォーマットに沿ったレポートを作成し、学校へ提出する際のフォローも行ってくれます。
これにより、保護者がすべての作業を負担する必要がなくなり、学校側への報告もスムーズに行うことができます。
すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる
すららでは、学校側との連携を円滑に進めるためのサポートも提供しています。
担任や校長先生とのコミュニケーションが不安な場合、どのように話を進めればよいのか、どのタイミングで何を伝えればよいのかなど、具体的なアドバイスを受けることができます。
これにより、学校側との意思疎通がスムーズになり、出席扱いの手続きがより確実に進められるようになります。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは、文部科学省の方針に沿った不登校支援の実績を持つ学習教材の一つです。
すでに全国の教育委員会や学校と連携し、不登校の子供たちの学習支援に活用されている実績があり、学校側もすららを活用することに対して一定の理解を持っています。
このような実績があることで、すららを使った学習が出席扱いとして認められやすくなっています。
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
すららは、全国のさまざまな自治体や学校と連携し、不登校の子供たちの学習支援を行ってきた実績があります。
これにより、すでにすららを導入している学校も多く、学校側がすららの学習システムに対して一定の理解を持っているケースが増えています。
すでに導入事例があることで、新しくすららを利用する子供も、学校側に説明しやすくなります。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
すららは、文部科学省が推奨する「ICTを活用した学習活動」の一環として、不登校支援教材として利用されています。
公式に認められた学習プログラムであるため、学校側も「どのような教材なのか」「どのような学習ができるのか」を理解しやすく、出席扱いとして認められやすい環境が整っています。
すららの公式サイトや教育委員会の資料を活用しながら、学校側と相談することで、よりスムーズに手続きを進めることができます。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
出席扱いとして認められるためには、「学校で学ぶのと同等の学習環境が整っていること」が重要な条件となります。
すららは、学習指導要領に沿ったカリキュラムを提供しており、学習の評価やフィードバックもシステム化されているため、学校での学習と同等の環境を実現できます。
このため、学校側もすららを使った学習が「学校に準ずる」と判断しやすくなり、出席扱いとして認めるケースが多くなっています。
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
すららのカリキュラムは、学校の学習指導要領に基づいて作成されているため、学校の授業と同じレベルの学習を進めることができます。
そのため、学校側も「独自の学習教材ではなく、指導要領に沿った学習が行われている」と判断しやすく、出席扱いとして認める理由になりやすいです。
また、無学年式のカリキュラムのため、学習の遅れを取り戻したり、得意な科目を伸ばしたりといった柔軟な学習も可能です。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
すららでは、学習の進捗や理解度を自動的に記録し、それに基づいて適切なフィードバックを提供するシステムが整っています。
これにより、学校の成績評価と同じように、子供がどの程度学習を進めているかを客観的に判断することが可能です。
学習の成果を数値化できるため、学校側も「ただ自宅学習をしているのではなく、きちんとした学習管理が行われている」と評価しやすくなります。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について
学校に通うことが難しい子供にとって、「出席扱い」制度は大きな助けになります。
文部科学省のガイドラインに基づき、オンライン学習を活用することで出席として認められる場合があります。
すららは、この出席扱いの要件を満たしやすい教材のひとつであり、多くの学校や教育委員会で導入実績があります。
しかし、出席扱いの申請は家庭ごとに対応が異なり、保護者が正しく手続きを進めることが重要です。
ここでは、出席扱いを申請する際の具体的な方法について解説します。
申請方法1・担任・学校に相談する
出席扱いを申請する最初のステップは、担任の先生や学校の担当者に相談することです。
出席扱いの基準は学校や自治体によって異なるため、まずは学校側にどのような手続きが必要なのかを確認することが重要です。
学校との円滑なコミュニケーションを取ることで、申請をスムーズに進めることができます。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
学校に相談する際には、出席扱いの申請に必要な書類や条件について詳しく聞くことが大切です。
一般的に、以下のような書類が求められることがあります。
・オンライン学習の記録(すららの学習履歴レポートなど)
・学習計画書(学習の進め方や進捗管理の方法を記載したもの)
・保護者の申請書(子供がオンライン学習を活用して学んでいることを説明する書類)
・学校が指定するその他の書類
また、出席扱いを認めるための条件も学校によって異なるため、「どれくらいの学習時間が必要か」「どのような評価基準があるのか」なども確認しておくと安心です。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
出席扱いの申請をする際、不登校の理由によっては医師の診断書や意見書が求められる場合があります。
これは、学校側が「子供がオンライン学習を活用しながら学習を継続することが望ましい」という医学的な意見を参考にするためです。
すべてのケースで診断書が必要なわけではありませんが、学校や自治体によっては提出を求められることがあるため、事前に確認しておきましょう。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
不登校の原因が、精神的なストレスや発達障害、適応障害などの医学的な理由によるものである場合、診断書の提出を求められることがあります。
特に、長期間学校に行けていない場合や、今後の学習方法について明確な方針を示すために、医師の意見書が重要になることがあります。
診断書の提出が必要かどうかは、学校と相談のうえ確認するとよいでしょう。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
診断書を用意する場合は、精神科・心療内科・小児科などの医師に相談し、「現在の不登校の状態」と「オンライン学習による学習継続が望ましいこと」を記載してもらうのが一般的です。
医師の診断書には、子供の精神的・身体的な状態や、どのような環境で学ぶことが適切かといった内容が書かれることが多いです。
学校側にとっても、医師の意見があることで出席扱いの判断がしやすくなるため、必要に応じて診断書の取得を検討するとよいでしょう。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
出席扱いとして認めてもらうためには、学校側に「どのように学習を継続しているか」を具体的に示す必要があります。
すららでは、学習の進捗状況を記録する機能があり、学習履歴をまとめたレポートを作成することができます。
このレポートを学校に提出することで、子供が継続的に学習していることを証明しやすくなります。
提出の際には、担任の先生や校長先生に相談し、どのような形で報告すればよいか確認するとスムーズです。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
すららでは、子供の学習時間や進捗状況が記録され、レポートとしてダウンロードできる仕組みがあります。
このレポートには、「どの科目をどのくらい学習したか」「どの単元まで進んでいるか」といった詳細な情報が含まれており、学校側に対して客観的な証拠を示すことができます。
レポートを担任や校長先生に提出することで、「家庭で適切な学習が行われている」ということを証明し、出席扱いの判断材料としてもらいやすくなります。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
学習記録と合わせて、出席扱いの申請書を学校で作成する必要があります。
申請書のフォーマットは学校によって異なるため、事前に担任の先生や事務担当者に確認しておくと安心です。
保護者としては、申請書の作成をサポートし、子供の学習状況や学習計画について補足説明を行うことが求められる場合があります。
特に、どのような環境で学習しているか、どのように進捗を管理しているかを明確に記載すると、学校側が判断しやすくなります。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
出席扱いが正式に認められるためには、学校長(校長先生)の承認が必要になります。
学校長が「適切な学習が行われている」と判断すれば、正式に出席扱いとして認められることになります。
また、自治体や学校によっては、教育委員会への申請が必要な場合もあるため、その場合は学校側と連携しながら進めることが重要です。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
出席扱いの最終的な判断は、学校長(校長先生)が行います。
すららの学習記録や申請書を提出し、学習の継続性や適切な進捗が認められれば、正式に「出席扱い」となります。
承認までの流れや基準は学校ごとに異なるため、事前に必要な手続きを確認し、しっかりと準備をしておくことが大切です。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
自治体によっては、出席扱いの判断を学校だけでなく、教育委員会が関与する場合もあります。
その場合は、学校と連携しながら、必要な書類をそろえて申請を進める必要があります。
教育委員会に申請する際は、学校側が主体となって進めることが多いため、保護者は学校とのやりとりをスムーズに進めることが重要です。
すららの学習記録や医師の診断書(必要な場合)などを準備し、学校と連携しながら申請を進めることで、出席扱いが認められる可能性が高まります。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します
不登校の子どもがオンライン学習を活用することで「出席扱い」として認められる制度は、学習の継続だけでなく、進学や自己肯定感の向上など、さまざまなメリットがあります。
すららは、この制度の条件を満たしやすい教材のひとつとして、不登校の子どもたちの学習を支えています。
出席扱いを認めてもらうことで、単に出席日数が増えるだけでなく、将来の選択肢が広がったり、親子の精神的な負担が軽減されたりと、多くの利点があります。
ここでは、すららを利用して出席扱いを認めてもらうことによる具体的なメリットについて詳しく紹介します。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
日本の学校では、成績評価の一部として「内申点」が重視されることが多く、特に中学校では高校進学の際に重要な指標となります。
内申点の評価には、学力だけでなく、出席日数も影響を与えるため、不登校の期間が長引くと、内申点の低下につながることがあります。
しかし、すららを活用して出席扱いを認めてもらえれば、出席日数を確保できるため、内申点が大きく下がるのを防ぐことができます。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
不登校が長期間にわたると、学校の成績とは別に「出席日数の不足」が問題となることがあります。
特に、定期的な試験で良い成績を取ったとしても、出席日数が極端に少ないと内申点が低くなる可能性があります。
すららを利用して出席扱いとして認められれば、学習の継続を証明できるため、出席日数の不足を補うことができます。
これにより、成績評価のバランスを維持しやすくなり、進学時に不利になりにくくなるのが大きなメリットです。
中学・高校進学の選択肢が広がる
内申点が一定以上あれば、進学時の選択肢が広がります。
高校受験では、学力試験の結果だけでなく、内申点も大きな影響を与えるため、出席扱いとして認められることはとても重要です。
すららを活用することで、学力の維持と出席日数の確保の両方が可能となり、希望する学校への進学をスムーズに進めることができます。
特に、公立高校の受験では内申点の比重が高いため、すららを利用して学習を継続しながら出席扱いを得ることは、大きなアドバンテージとなります。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
不登校の子どもにとって、「学校の授業についていけなくなるのでは」という不安は大きなものです。
一度学習が遅れてしまうと、「もう追いつけない」と感じてしまい、ますます勉強への意欲を失ってしまうこともあります。
しかし、すららは無学年式のカリキュラムを採用しており、子どもの理解度に合わせて自由に学習を進められるため、「遅れを取り戻せない」という不安を軽減することができます。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
すららは、学年にとらわれず、自分のペースで学習できるシステムになっています。
そのため、「前の学年の内容を復習しながら学び直したい」「今の学年の単元をゆっくり進めたい」といった個別のニーズに応じて学習計画を立てることができます。
これにより、学校に行かなくても学習の遅れを心配せずに済み、無理なく勉強を続けることができます。
また、学校復帰を考えている場合も、必要な単元をしっかり学んでおくことで、復帰後にスムーズに授業に参加しやすくなります。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
不登校が長引くと、「勉強ができない自分」「みんなと違う自分」といったネガティブな感情を抱きやすくなります。
しかし、すららを活用すれば、「自分のペースで学習できている」「確実に知識が増えている」と実感しやすくなり、自己肯定感の低下を防ぐことができます。
また、すららにはコーチがいるため、一人で勉強しているわけではなく、誰かが見守ってくれているという安心感も得られます。
こうした環境が整うことで、子どもが前向きな気持ちで学習を続けやすくなります。
メリット3・親の心の負担が減る
不登校の子どもを持つ親にとって、「どうやって学習を進めさせるか」「将来の進学に影響が出るのではないか」といった悩みは尽きません。
特に、出席扱いの制度を活用しようとすると、学校とのやり取りや書類の準備など、親の負担が大きくなることがあります。
しかし、すららは学校との連携をサポートし、学習記録の提出や計画作成を手助けしてくれるため、親の負担を大幅に軽減することができます。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
すららには、学習の進め方をサポートする「すららコーチ」がいます。
このコーチは、子どもの学習計画を立てるだけでなく、学習の進捗を管理し、必要に応じてアドバイスを提供してくれる存在です。
これにより、親がすべてを管理しなくても、子どもが無理なく学習を続けることができます。
また、学校とも連携しやすくなるため、親が一人で不安を抱えることなく、安心して学習を進められる環境が整います。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します
不登校の子どもがすららを利用して出席扱いを認めてもらうには、いくつかの注意点があります。
文部科学省のガイドラインでは、オンライン学習を活用することで出席扱いが認められるケースがあるとされていますが、実際には学校ごとの判断が大きく影響します。
そのため、学校側の理解を得ることや、必要な書類をしっかり準備することが重要です。
事前の準備や正しい申請手続きを行わないと、出席扱いが認められない可能性もあるため、注意点を押さえておくことが大切です。
ここでは、すららで出席扱いを申請する際に気をつけるべきポイントについて詳しく紹介します。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
すららを利用して出席扱いを認めてもらうためには、学校側の理解を得ることが欠かせません。
出席扱いの判断は、最終的に校長先生の裁量に委ねられるため、学校全体の協力が必要です。
特に、オンライン学習による出席扱いに詳しくない学校もあるため、「すららが文部科学省のガイドラインに沿った教材であること」を丁寧に説明し、学校側に安心してもらうことが重要です。
また、担任の先生だけでなく、教頭先生や校長先生とも早めに相談し、出席扱いの可能性について話し合うことが大切です。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
すららは、文部科学省が示す「ICTを活用した学習支援」の対象となる教材のひとつです。
しかし、学校によっては、オンライン学習を出席扱いとして認める基準に詳しくない場合もあります。
そのため、「すららは文部科学省のガイドラインに基づいた教材である」ということを丁寧に説明し、学校側の理解を得ることが大切です。
具体的には、すららが学習指導要領に沿ったカリキュラムを提供していること、学習記録が残る仕組みになっていること、専任コーチによるサポートがあることなどを伝えると、学校側も安心しやすくなります。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
学校との話し合いをスムーズに進めるためには、すららの公式サイトからダウンロードできる資料を持参し、具体的な内容を説明することが効果的です。
特に、「どのように学習を進めているのか」「学校の授業と同じ学習指導要領に沿っていること」を示すことで、学校側が出席扱いとして認めやすくなります。
また、担任の先生だけでなく、教頭先生や校長先生とも早めに相談し、学校全体としての判断を仰ぐことが重要です。
出席扱いの申請は時間がかかることもあるため、できるだけ早めに動き出すことが大切です。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
不登校の原因によっては、学校側から医師の診断書や意見書の提出を求められることがあります。
特に、「体調不良」や「精神的な理由」による不登校の場合、学校が出席扱いを認めるための判断材料として、医師の診断書を必要とするケースが多いです。
医師の診断書には、「現在の健康状態」「登校が難しい理由」「家庭学習の必要性」などが記載されるため、事前にどのような内容を記載してもらうべきかを確認し、適切な手続きを進めることが重要です。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
出席扱いの申請では、「なぜ学校に通えないのか」を明確にすることが求められます。
特に、心因性の不登校や体調不良による欠席の場合、医師の診断書があることで、学校側が「登校が難しい正当な理由がある」と判断しやすくなります。
診断書には、「学習を継続することが望ましい」という内容が含まれていると、学校側も前向きに検討しやすくなります。
そのため、診断書が必要かどうかを事前に学校に確認し、求められた場合は速やかに医師に相談することが大切です。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
診断書を発行してもらう際には、通っている小児科や心療内科の医師に「出席扱いの申請に必要な診断書が欲しい」と具体的に伝えることが重要です。
医師によっては、どのような内容を書けばよいのか分からない場合もあるため、「学校に提出するために、家庭学習が適していることを証明してほしい」など、具体的に伝えるとスムーズです。
診断書には、子どもの現状だけでなく、学習を継続する意欲があることも記載してもらうと、学校側が承認しやすくなります。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
医師に診断書を作成してもらう際には、単に「不登校の状態である」と記載するのではなく、「すららを活用して学習を継続していること」「家庭学習の環境が整っていること」「学習を続けることで精神的に安定していること」など、具体的な内容を盛り込んでもらうと、学校側の理解を得やすくなります。
そのため、診断書の発行をお願いする際には、子どもがどのような形で学習を続けているかを医師にしっかり伝え、できるだけ前向きな内容で記載してもらうようにしましょう。
注意点3・学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
出席扱いを認めてもらうためには、学習の質と量が「学校の授業に準ずるレベル」であることが求められます。
ただ単に自宅で勉強しているだけでは、学校側が「授業と同等の学習が行われている」と判断しにくいため、注意が必要です。
特に、学習内容が学校のカリキュラムと大きく異なっていたり、学習時間が極端に少なかったりすると、出席扱いが認められないことがあります。
そのため、すららを活用しながら、適切な学習時間とバランスの取れた教科学習を意識することが大切です。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
学校が出席扱いを認めるためには、「家庭学習が学校の授業に準じているかどうか」が重要なポイントになります。
単なるドリル学習や、好きな教科だけを学ぶスタイルではなく、すららのように学校の学習指導要領に沿った教材を使用し、体系的に学習を進めることが必要です。
また、授業で学ぶべき単元を網羅しながら、適切な進度で学習を進めていることを証明することも大切です。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
学習時間の確保も、出席扱いの判断基準のひとつになります。
一般的に、小中学校では1日5時間以上の授業が行われていますが、家庭学習の場合はそのすべてを再現する必要はありません。
ただし、あまりに短時間では「学習の継続性が確保されていない」と判断される可能性があるため、目安として1日2〜3時間程度の学習を行うとよいでしょう。
すららでは、スモールステップでの学習が可能なため、短時間でも集中して学べる環境が整っています。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
出席扱いを認めてもらうためには、特定の教科だけでなく、全教科をバランスよく学習することも重要です。
特に、国語・数学(算数)・英語・理科・社会など、主要教科に偏らずに、幅広く学ぶことが求められます。
学校によっては、美術や体育、音楽などの副教科についても何らかの学習活動を求める場合があるため、あらかじめ学校側に確認しておくと安心です。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
出席扱いとして認められるためには、「学習状況が学校と共有されていること」が条件になることが多いです。
そのため、一度申請が通ったからといって終わりではなく、継続的に学校と連絡を取りながら、学習の進捗を報告する必要があります。
特に、担任の先生とのやり取りを大切にし、必要に応じて家庭訪問や面談にも対応することが、スムーズな申請につながります。
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
学校側が家庭学習の状況を把握できなければ、出席扱いを継続することが難しくなる場合があります。
そのため、定期的に学習の進捗を報告し、学校と情報共有を行うことが大切です。
すららを利用すれば、学習記録が自動で保存されるため、こうした報告もスムーズに行うことができます。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
学習の進捗を学校側に示すために、すららの学習レポートを月に1回程度提出するのが望ましいです。
このレポートには、学習した科目や単元、学習時間などが記録されており、学校側に「どのような学習を行っているか」を具体的に伝えることができます。
学習レポートを提出することで、学校側も安心して出席扱いを認めやすくなります。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
学校によっては、家庭訪問や面談を通じて学習状況を確認することがあります。
これは、学校側が「家庭学習がしっかり行われているか」を確認するためのものであり、特に不登校支援に積極的な学校では、こうした面談を重視する傾向があります。
もし学校側から面談の要請があった場合は、すららでの学習状況や学習計画について説明できるように準備しておくと安心です。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
学習の進捗を学校側とスムーズに共有するためには、担任の先生とのコミュニケーションを密にすることが重要です。
定期的にメールや電話でやり取りを行い、学習の進捗や困っている点などを相談することで、学校側も状況を把握しやすくなります。
特に、出席扱いの条件として「定期的な報告」が求められる場合は、学校との信頼関係を築くためにも、積極的に連絡を取ることをおすすめします。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
自治体によっては、出席扱いの申請を学校だけでなく、教育委員会にも提出しなければならない場合があります。
この場合、必要な書類の準備や申請手続きが複雑になることもあるため、学校と連携しながら進めることが大切です。
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
教育委員会への申請が必要な場合は、学校側と相談しながら必要な資料を準備することが重要です。
一般的には、学習計画書や学習レポート、医師の診断書などが求められることが多いため、事前に確認しておくとスムーズです。
自治体によって申請方法が異なるため、学校側と密に連携を取りながら、適切な書類を整えていくことが大切です。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します
不登校の子供が「出席扱い」として認められるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。
学校や教育委員会が出席扱いを判断する際には、学習の質や継続性、本人の意欲などを総合的に考慮します。
すららは、文部科学省のガイドラインに基づいた学習教材であり、全国で多くの出席扱い実績がありますが、スムーズに申請を進めるためには、学校側にしっかりと説明し、学習状況を明確に示すことが重要です。
ここでは、出席扱いを認めてもらうための成功ポイントについて紹介します。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
学校側が出席扱いの申請を検討する際、「過去に同じようなケースがあったかどうか」が大きな判断材料になることがあります。
すららを活用して出席扱いが認められた実績が全国にあるため、それを学校側に伝えることで、前向きに検討してもらいやすくなります。
特に、校長先生や教育委員会は、前例があることを確認できると安心しやすいため、実績を示すことがポイントになります。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
学校側に説明する際、すららで出席扱いが認められた他の学校の事例を紹介すると、より説得力が増します。
「他の自治体や学校でも同様のケースがある」という事実を伝えることで、学校側も制度の活用を前向きに検討しやすくなります。
事例を具体的に提示することで、学校側が「前例があるなら、自校でも可能かもしれない」と考えやすくなるのです。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
すららの公式サイトでは、過去に出席扱いが認められた事例が紹介されていることがあります。
これらの情報をプリントして学校に持参し、担任や校長先生に見せることで、よりスムーズに話を進めることができます。
また、学校側が制度に詳しくない場合でも、具体的な事例を見せることで理解を得やすくなります。
可能であれば、すららのサポートセンターに問い合わせて、出席扱いに関する具体的な資料を提供してもらうのも良い方法です。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
出席扱いを認めてもらうためには、「本人が学習を継続する意思を持っていること」を示すことが重要です。
学校側は、家庭学習が続くかどうかを懸念することが多いため、「本人が前向きに取り組んでいる」という証拠を示すことで、出席扱いを認めやすくなります。
保護者だけが申請を進めるのではなく、本人の意欲をアピールすることが成功の鍵となります。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
学校側に学習状況を報告する際、本人が書いた学習の感想や目標を提出すると、より説得力が増します。
「どのような内容を学習しているのか」「どのような目標を持っているのか」といった本人の声を伝えることで、学校側も「自主的に学習を続けている」と判断しやすくなります。
また、目標を設定することで、学習に対する前向きな姿勢を示すことができます。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
学校との面談がある場合、できるだけ本人も参加し、自分の言葉で学習への意欲を伝えることが望ましいです。
「今は学校に通えないけれど、すららを活用して学習を続けている」「将来的には学校に戻りたいと思っている」など、前向きな姿勢を見せることで、学校側の理解を得やすくなります。
本人の意志をしっかり伝えることで、学校側も安心し、出席扱いの申請をスムーズに進めることができます。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
出席扱いを認めてもらうためには、「学習が継続できること」が非常に重要です。
短期間だけ学習を頑張っても、途中で続かなくなってしまうと、学校側が出席扱いの判断を見直す可能性もあります。
そのため、本人に無理のない学習計画を立て、継続的に学習を進めることがポイントになります。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
学習計画を立てる際は、本人のペースに合わせた無理のないスケジュールを組むことが大切です。
急に長時間の学習を課すのではなく、1日1時間からスタートし、徐々に学習時間を増やしていくと、無理なく継続しやすくなります。
計画的に学習を進めることで、学校側にも「継続して学習している」と認めてもらいやすくなります。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
すららには、学習の進め方をサポートする「すららコーチ」がいます。
学習計画の立て方に悩んだ場合は、すららコーチに相談し、本人に合った現実的なスケジュールを一緒に考えてもらうとよいでしょう。
学校側に提出する学習計画書を作成する際にも、すららコーチのアドバイスを受けながら進めることで、より適切な計画を立てることができます。
ポイント4・「すららコーチ」をフル活用する
すららには、学習の進捗管理やレポート作成をサポートする「すららコーチ」がいます。
出席扱いの申請を進める際、コーチのサポートを活用することで、学校側への説明や必要書類の準備がスムーズになります。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
出席扱いを申請する際には、学習の進捗を示すレポートや学習証明が必要になることが多いですが、これらの書類はすららコーチがサポートしてくれます。
学習の進め方や記録の管理に不安がある場合は、積極的にコーチに相談し、適切な資料を準備するとよいでしょう。
すららコーチのサポートを活用することで、学校側の理解を得やすくなり、出席扱いの申請をスムーズに進めることができます。

すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
スララはウザいという口コミがある背景には、いくつかの理由が考えられます。
まず一つ目に挙げられるのは、スララのサービス内容が一部のユーザーにとって適していない可能性がある点です。
個々のニーズや好みは異なるため、全てのユーザーにとって理想的なサービスとは言えません。
そのため、中にはスララのサービスが合わないと感じる方もいるかもしれません。
また、コミュニケーションの取り方や情報の提供方法に関する違いも、ウザいと感じられる要因となるかもしれません。
スララが提供する情報やサポートが、一部のユーザーにとって過剰に感じられる場合があります。
そのような場合には、ユーザー側からは「ウザい」と感じる可能性が高まります。
さらに、過度なプッシュやスパムのような行為が、ユーザーにとってストレスをもたらす場合も考えられます。
スララが情報提供やサービスの案内を行う際に、過剰なアプローチを取ってしまうと、ユーザーたちが不快に感じることも十分に考えられます。
このように、スララがウザいと感じられる口コミがある背景には、様々な要因が絡んでいる可能性があります。
ユーザーの意見や感想は多様であり、それぞれの視点から捉えることが重要です。
スララはユーザーの声に真摯に向き合い、サービス向上に取り組むことが重要であると言えます。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららの発達障害コースの料金プランについてお知らせいたします。
すららでは、発達障害のあるお子様向けに専門的なコースを提供しており、料金プランも慎重に設計されています。
コース内容やサポート体制に加えて、料金に関する詳細をご説明いたします。
まず、すららの発達障害コースは、個々のお子様のニーズに合わせてカスタマイズされています。
そのため、料金は個別のケースによって異なります。
料金には、指導・サポート費用や各種教材費などが含まれており、お子様の発達段階や状況に基づいて柔軟に調整されます。
また、すららでは透明性を大切にし、料金に関する詳細を十分にご説明いたします。
初回のカウンセリングや面談を通じて、コースの内容や料金プランについてお伝えし、お子様とご家族が納得いくまでご相談させていただきます。
適切なサービスを提供するために、お子様やご家族のご要望やご質問に真摯にお答えいたします。
ご不明点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
すららでは、お子様の成長と発達に貢献できるよう最善を尽くしてまいります。
お子様の明るい未来を一緒にサポートできることを心より楽しみにしております。
関連ページ: すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
すららのタブレット学習プログラムを利用している不登校の子供の保護者の皆様からよくいただく質問の一つに、「すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになるのでしょうか」というものがあります。
これに関して、すららのタブレット学習は個々の学校や地域の方針により異なりますので、一概には申し上げかねますが、一般的に言えることをご説明いたします。
不登校の子供がすららのタブレット学習を利用して学習を行った場合、その時間や進捗状況などはスクール等での出席扱いとして認められる場合があります。
しかし、これは学校や教育委員会などの判断や方針に左右される重要な要素でございます。
不登校の子供がすららのタブレット学習を活用する際には、保護者の方々と学校側との密な連携が求められます。
学校の了解を得ることが重要であり、出席扱いになるかどうかはその状況によるものであります。
このような場合、保護者や担当の先生方と協力し合いながら、子供の学習環境を整え、定期的な進捗報告や連絡を行うことが肝要です。
不登校の子供でも、すららのタブレット学習を通じて十分な学びを得ることができ、出席扱いになることもあり得るのです。
一方で、すべての学校や地域で同じ方針が適用されるわけではないため、不登校の子供がすららのタブレット学習を出席扱いと認められるかどうかについては、事前に該当する学校や関係機関への確認が必要です。
その際は、丁寧にご相談いただき、子供のために最善のサポートが受けられるよう努めてまいりましょう。
関連ページ: すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
今日は、すららのキャンペーンコードの使い方についてご案内いたします。
すららは、日本で最大のオンライン学習プラットフォームの1つです。
キャンペーンコードを利用することで、さらにお得に学習コースを受講することが可能です。
すららのキャンペーンコードの使い方を詳しく説明いたします。
まず、キャンペーンコードを入力する際には、決済画面での入力欄がございますので、そちらにキャンペーンコードを入力してください。
その後、適用ボタンを押すことで、割引が適用されます。
お支払い金額が変更されたら、正しくキャンペーンコードが適用されたことが確認できます。
是非この機会に、お得にすららの学習コースをご利用ください。
どうぞお楽しみください。
関連ページ: すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららを退会する際の手続きについて詳しく説明いたします。
まず、退会手続きを行う際には、すべてのアカウントの情報やデータを確認し、必要に応じてバックアップを取得することをお勧めします。
次に、すららのウェブサイトにログインし、「アカウント設定」や「会員情報」などのメニューをクリックしてください。
そこから、「退会」や「アカウント削除」などの項目を選択し、指示に従って手続きを進めてください。
退会手続きが完了すると、アカウントは削除され、すららのサービスを利用することができなくなります。
退会後も再登録が可能な場合もありますが、詳細はお問い合わせ先にてご確認いただくことをお勧めします。
すららをご利用いただき、誠にありがとうございました。
関連ページ: すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららをご検討いただき、ありがとうございます。
すららでは、入会金と月謝以外に追加の料金は発生いたしません。
お支払いいただくのは、入会時の初期費用と、毎月の受講料のみとなります。
当サービスをご利用いただく際には、安心してお子様の学習環境を整えることができます。
何かご不明点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ますますのご活躍をお祈り申し上げます。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
1人の受講料を支払う際に兄弟で一緒に利用することは可能でしょうか。
この点について、教育機関ごとに異なる方針がある場合がございますので、ご確認いただくことをお勧めいたします。
一般的に、受講料は一人ひとりに対して支払う仕組みとなっておりますが、ご家族間でシェアする場合も一部の機関では認められている場合があります。
ただし、ルールや条件がある可能性がございますので、事前に教育機関にお問い合わせいただくことをおすすめいたします。
兄弟での利用が許可されている場合でも、手続きや制約について事前に確認しておくことが重要です。
詳細については、ご指定の教育機関に直接お問い合わせいただき、その方針についてご確認ください。
すららの小学生コースには英語はありますか?
すららの小学生コースには英語はありますか?このご質問にお答えするために、すららの小学生コースでは、英語は今のところ提供しておりません。
弊社の小学生コースは、主に日本の小学校向けに日本語の学習教材を提供しております。
しかし、英語に関心のある生徒の皆様には、将来的に英語コースの拡充も検討しております。
日本語教育にフォーカスし、基礎固めを大切にしておりますが、英語教育にも対応できる体制を整える予定です。
お客様のご要望にお応えできるよう努めてまいりますので、今後ともすららをご愛顧いただけますようお願い申し上げます。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららのコーチからは、言語学習において幅広いサポートを受けることができます。
専門的な知識と経験豊富なコーチが、生徒一人ひとりにあわせたカスタマイズされた指導を行います。
コーチは、文法、発音、語彙などの言語技能向上のためのアドバイスや補助を提供します。
さらに、学習計画や目標設定の面でも的確なアドバイスを行い、生徒が効果的に成長できるようサポートします。
すららのコーチは、生徒のニーズや進捗に合わせて柔軟に対応し、適切なガイダンスを提供することで、効果的な学習環境を構築します。
生徒が抱える疑問や悩みに丁寧に応えることで、学習意欲の向上と自信の醸成をサポートいたします。
すららのコーチは、あなたの言語学習を真剣にサポートし、確実な成長へと導いてくれるでしょう。
参照: よくある質問 (すらら公式サイト)

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ
今回のテーマは、「すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ」でした。
不登校の生徒が出席扱いになるためには、特定の手続きや制度を理解することが重要です。
出席扱いを受けるためには、まずは学校や教育委員会などに相談し、手続きや必要な書類について確認することがポイントです。
また、出席扱いを受ける際には、不登校の理由や期間、状況などを詳細に説明することが求められます。
出席扱いの申請手順や注意点をしっかり把握することで、円滑な手続きが可能となります。
不登校でも出席扱いになることで、学校生活や進路における影響を最小限に抑えることができるでしょう。
しかし、注意点も忘れずに確認し、適切な対応を心がけることが大切です。
不登校の生徒が出席扱いになることは、その子供の将来にとっても重要な要素となります。
制度や手続きを正しく理解し、適切に対応することで、不登校期間中も学習の遅れを最小限に抑え、スムーズに学校生活に復帰することができるでしょう。
不登校支援の制度を活用しながら、生徒一人ひとりの成長と学びを大切にしていきましょう。

