すららはうざい!?すららが選ばれるおすすめのポイントを紹介します
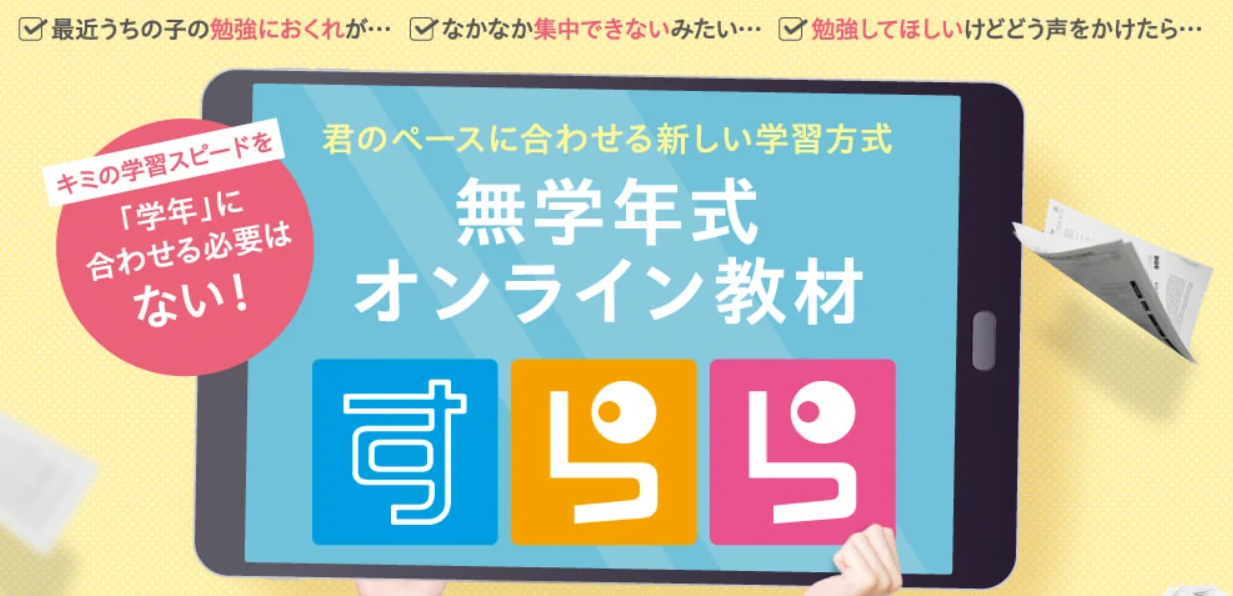
「すららはうざい」という声を目にすることがありますが、それは本当にそうなのでしょうか?すららは、学年に縛られず自由に学べる無学年式や、アニメキャラクターとの対話型授業など、他のオンライン学習にはない魅力を持っています。
特に、発達障害や不登校の子どもにも対応している点が評価されており、学習のつまずきをAIが解析してフォローする仕組みも整っています。
この記事では、そんなすららのおすすめポイントを詳しく紹介していきます。
すららがどんな学習スタイルなのかを知り、自分やお子さんに合った学び方を見つける参考になればうれしいです。
すららのおすすめポイントをまとめました
すららには、他のオンライン学習教材にはない魅力的なポイントがたくさんあります。
ここでは、すららの主な特徴を表にまとめました。
| ポイント | 具体例 |
| 無学年式 | 小1の子が中学英語も学べる!苦手もじっくり戻れる |
| 対話型授業 | アニメキャラとの対話形式で「双方向」学習 |
| すららコーチ | 親がスケジュール管理しなくてOK!丸投げ可能 |
| 発達障害・不登校対応 | AIがつまずきを解析→無理なく学習再開できる |
| 成果が見える | テスト・レポート・定着診断で、親も安心 |
| 英語3技能対応 | 話す・聞く・読むがまんべんなく学べる |
| 兄弟OK | 1契約で複数人OK→家族で使えば超コスパがいい |
ポイント1・無学年式!学年に縛られず、得意も苦手も自由に学べる
すららの最大の特徴の一つが「無学年式」の学習スタイルです。
学校では、学年ごとに決められた範囲の勉強を進めるため、苦手な部分があるとそのまま置いていかれてしまうことがあります。
しかし、すららでは学年に関係なく学習できるので、自分の得意・不得意に応じて自由に進めることができます。
たとえば、数学が得意な子ならどんどん先に進み、苦手な子は基礎からじっくり学び直せるのが魅力です。
学力や進度に関係なく、自分のペースで学べる
学校の授業では、クラス全員が同じペースで進むため、一度つまずいてしまうとそのまま苦手意識が生まれてしまうことがあります。
しかし、すららの無学年式なら、自分の理解度に合わせて学習できるので、焦ることなくじっくり学ぶことが可能です。
逆に、得意な分野は学年に関係なく先取りできるため、「勉強がつまらない」と感じることなく、学習意欲を維持しやすいのも特徴です。
「得意はどんどん進める」「苦手はじっくり戻る」が簡単にできる
すららでは、過去の学年の内容にさかのぼって復習することができます。
たとえば、小学5年生の子が「分数の計算が苦手」と感じた場合、小学3年生の基礎から戻って学ぶことができるのです。
逆に、得意な教科ではどんどん先の学年の内容を学習することも可能です。
この柔軟な学習スタイルにより、一人ひとりに合った勉強ができるのがすららの強みです。
ポイント2・「対話型アニメーション授業」で、わかりやすい&飽きない
すららのもう一つの特徴は、「対話型アニメーション授業」です。
通常のオンライン教材は、テキストや動画を見るだけの学習が多いですが、すららはアニメキャラクターが先生役となり、子どもと会話しながら進めてくれます。
この双方向型の学習スタイルが、子どもたちの理解度を深め、飽きずに続けられる秘訣となっています。
アニメキャラが「先生役」として、子どもと会話しながら進めてくれる
すららの授業は、アニメーションのキャラクターが先生役を務め、子どもに質問を投げかけたり、ヒントを出したりしながら進んでいきます。
まるで本当に先生と会話しているような感覚で学習できるので、一方的に説明を聞くよりも理解しやすくなります。
「ただ聞くだけ」の授業ではなく、「自分で考えて答える」機会があることで、学習効果が高まります。
難しいことも「図や動き」で視覚的に理解できる
特に算数や理科のような、概念的な内容を理解するのが難しい科目では、図やアニメーションの動きを活用することで、直感的に学ぶことができます。
たとえば、分数の計算を学ぶときには、ケーキやピザを切るアニメーションを使って、「半分」「4分の1」などの概念をわかりやすく説明してくれます。
このように、視覚的に学べることで、文章だけでは理解しづらい内容もスムーズに頭に入ってきます。
キャラが褒めてくれるからやる気UP!飽きっぽい子でも続きやすい
すららのキャラクターは、子どもが正解するとしっかり褒めてくれます。
「よくできたね!」「すごいね!」といった声掛けがあることで、子どもは「もっと頑張ろう」という気持ちになりやすくなります。
特に、飽きっぽい子や勉強に苦手意識がある子にとって、褒められながら学べる環境はモチベーション維持に効果的です。
ポイント3・「すららコーチ」がついて親の負担が激減
オンライン学習を導入すると、親が「ちゃんと続けられるか心配」「スケジュール管理が大変」といった悩みを抱えることがあります。
すららでは、「すららコーチ」と呼ばれる学習サポートのプロがついてくれるため、親の負担が大幅に軽減されます。
コーチが子どもの学習計画を作成し、進捗を管理してくれるので、親が細かくチェックしなくても安心です。
プロの「すららコーチ」が学習計画を作成&フォローしてくれる
すららコーチは、子ども一人ひとりの学力やペースに合わせた学習計画を作成してくれます。
「今日はこの範囲をやろう」「この単元をもう少し復習しよう」といった具体的な学習指示があるため、子どもも迷わずに勉強を進めることができます。
また、学習が計画通りに進んでいるかどうかもコーチがチェックしてくれるため、つまずいたときには適切なアドバイスを受けることができます。
子どもの特性や希望に合わせたオーダーメイド学習計画を立ててくれる
すららコーチは、単に「この日までにここを終わらせる」といった機械的な計画を立てるのではなく、子どもの性格や学習ペースを考慮して、オーダーメイドの学習計画を作成してくれます。
「じっくり理解したい」「短時間で効率よく進めたい」など、それぞれの学習スタイルに合わせた指導が受けられるため、無理なく続けることができます。
質問や相談はコーチに直接できるから親は見守るだけでOK
すららコーチには、学習についての質問や相談を直接することができます。
「この問題の意味がわからない」「もっと効果的な勉強方法を知りたい」といった疑問にも、プロが的確にアドバイスをしてくれるため、子どもが一人で悩むことがありません。
親がわざわざ教えたり、スケジュールを管理したりする必要がなくなるので、仕事や家事で忙しい家庭でも安心して利用できます。
ポイント4・発達障害・不登校にも対応!学習への不安を取り除いてくれる
すららは、発達障害や不登校の子どもたちにも対応した学習支援ツールとして、多くの家庭や教育機関で活用されています。
一般的なオンライン学習では、自分のペースで進められない、理解が追いつかないといった問題が生じることがありますが、すららはそうした課題を解決するための工夫がされています。
学び直しができる無学年式や、AIを活用したつまずきのフォローなど、一人ひとりの学習状況に合わせたサポートが充実しているのが特徴です。
文部科学大臣賞も受賞している学習支援ツール
すららは、その教育的な価値が認められ、文部科学大臣賞を受賞しています。
この賞は、優れた教育コンテンツに与えられるもので、すららが学習効果の高い教材であることを証明しています。
単なるオンライン教材ではなく、子どもの理解度に寄り添いながら学べる仕組みが評価され、全国の学校や塾でも導入が進んでいます。
発達障害(ADHD、学習障害など)の子にも適した設計で安心
すららは、発達障害を持つ子どもたちでも学びやすいように設計されています。
例えば、ADHD(注意欠如・多動症)の子どもにとっては、長時間集中するのが難しいことがありますが、すららの授業はアニメーションを活用し、対話形式で進められるため、飽きにくい工夫がされています。
また、学習障害(LD)を持つ子どもにとっては、視覚的に理解しやすい図や動きがサポートとなり、無理なく学習を続けることができます。
不登校で学校の授業に追いつけない子でも取り組みやすい
不登校の子どもにとって、学校の授業に復帰する際の大きな壁となるのが「勉強の遅れ」です。
すららなら、無学年式のシステムを活かして、必要な単元に戻って学び直すことができるため、学校の授業に追いつくための学習がしやすくなります。
さらに、対話型アニメーション授業なので、先生に質問しにくい子どもでも気軽に学習を進めることができるのが魅力です。
つまづきをAIが解析→理解不足の箇所を自動で出題してくれる
すららは、AIを活用して子ども一人ひとりの学習状況を分析し、どこでつまずいているのかを自動的に解析します。
その結果に基づいて、理解が不十分な部分を重点的に出題してくれるため、「苦手なまま進んでしまう」ことがありません。
こうした仕組みのおかげで、発達障害や不登校の子どもでも、自分のペースで無理なく学習を続けることができます。
ポイント5・オンラインテスト&リアルタイム学力分析で、成果が見える
すららでは、学習の成果をしっかり確認できる仕組みも整っています。
オンライン学習では、「本当に身についているのか分からない」「親が学習の進捗を把握しづらい」といった悩みが出てくることがありますが、すららはテストやAI分析を通じて、学習の定着度を可視化できます。
これにより、子ども自身も成長を実感しやすく、学習のモチベーションを維持しやすくなっています。
小テストで間違えた問題を即フィードバックできる
すららでは、各単元ごとに小テストが用意されており、学習の成果をすぐに確認することができます。
もし間違えた場合も、即座に解説が表示されるため、「なぜ間違えたのか」を理解しながら学習を進めることが可能です。
このような即時フィードバックの仕組みがあることで、ただ問題を解くだけではなく、しっかりと理解しながら学習を進められます。
定着度診断でAIがどこが苦手か把握し即対策問題を出してくれる
すららには「定着度診断」という機能があり、AIが子どもの学習状況を分析し、苦手な部分を特定してくれます。
そして、その結果に基づいて、子どもに最適な復習問題が自動的に出題されるため、「どこを重点的に復習すればいいのか」が明確になります。
これにより、無駄のない学習ができるだけでなく、苦手克服もしやすくなります。
保護者にもレポート配信し「何をどこまで理解しているのか」をしっかり確認できる
オンライン学習では、親が「本当に勉強しているのか」「どれくらい成績が伸びているのか」を把握しにくいことがあります。
すららでは、学習の進捗や理解度をまとめたレポートが定期的に配信されるため、親も安心して見守ることができます。
「どの単元が得意なのか」「どこでつまずいているのか」が可視化されることで、家庭でも適切なサポートがしやすくなります。
ポイント6・英語が「リスニング」「リーディング」「スピーキング」の3技能対応
すららの英語学習は、単なる「読む・書く」だけではなく、「リスニング」「リーディング」「スピーキング」の3技能をバランスよく学べるのが特徴です。
学校の授業や一般的なオンライン教材では、リーディングと文法に偏りがちですが、すららなら実践的な英語力を身につけることができます。
英語が苦手な子も、得意な子も、自分のレベルに合わせてしっかりと学習できるのが魅力です。
ネイティブ音声のリスニングを学ぶことができる
すららの英語教材では、ネイティブスピーカーの音声を使用しており、本物の発音を聞きながらリスニングのトレーニングができます。
日本の英語教育では、リスニングの機会が少ないことが課題とされていますが、すららなら日常的にネイティブの発音に触れることができるため、英語の音に慣れることができます。
学校のリスニングテストや英検のリスニング対策にも効果的です。
音読チェックでスピーキング練習ができる
英語を話せるようになるためには、「聞く」だけでなく「話す」練習も欠かせません。
すららでは、音読チェック機能があり、自分の発音を確認しながらスピーキングの練習ができます。
「自分の英語が通じるか不安…」という子どもでも、気軽に発音練習ができるため、スピーキング力を自然と伸ばすことができます。
英語を「学ぶ」だけでなく、「使う」練習ができるのが魅力です。
単語・文法もアニメーションで丁寧に解説してくれるから英検対策におすすめ
英語を習得する上で欠かせないのが、単語と文法の理解です。
すららでは、これらをアニメーションを使ってわかりやすく解説してくれるため、暗記が苦手な子どもでもスムーズに学ぶことができます。
英検の各級に対応した単語や文法も学習できるので、英検対策にも最適です。
「英語の勉強は難しい…」と感じる子どもでも、楽しみながら学習を進めることができます。
ポイント7・料金体系が「1人分じゃない!」兄弟OK&科目追加自由
すららの料金体系は、他のオンライン学習サービスと比べても非常にお得です。
多くのオンライン教材は1人分の契約ごとに料金がかかることが一般的ですが、すららは1つの契約で兄弟姉妹が一緒に利用できます。
また、科目ごとに自由に追加・変更ができるため、無駄なく学習を進められるのが大きなメリットです。
1つの契約で兄弟同時利用OK!(人数分の追加料金なし)
すららは、1つの契約で複数の兄弟姉妹が同時に利用できるため、家族での学習にぴったりです。
たとえば、「兄は数学、妹は英語を学びたい」といった場合でも、追加料金なしでそれぞれの学習を進められます。
一般的なオンライン教材では、1人ずつ契約する必要があるものが多いですが、すららなら家族で学習コストを抑えられるのが大きな魅力です。
小学生の兄と中学生の妹、同じ契約内で利用できるからコスパがいい
兄弟の学年が異なると、それぞれのレベルに合った教材を用意する必要がありますが、すららなら無学年式のシステムを活かして、異なる学年の子どもが同じ契約内で学習できます。
たとえば、小学生の兄が算数を学びながら、中学生の妹が英語を学ぶといった使い方も可能です。
「年齢が違うから、それぞれ別の教材を契約しなければならない…」と悩んでいた家庭にとっては、コストを抑えつつ最適な学習環境を整えられるのがメリットです。
科目ごとに選んで追加できるから、無駄がない
すららでは、必要な科目だけを選んで追加できるため、「全部の科目を契約するのはもったいない」と感じている方にもおすすめです。
「数学だけを強化したい」「英語を中心に学びたい」といった個別のニーズに応じて、最適な学習プランを組むことができます。
これにより、無駄なく効率的に学習を進めることができるため、家庭の学習環境に合わせた柔軟な使い方が可能です。

【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材にはないすららのメリットについて
「すららはうざい」といった意見を見かけることもありますが、実際には多くの家庭で高い評価を受けているオンライン学習教材です。
他の家庭用タブレット教材と比べて、すららにはどのようなメリットがあるのでしょうか?本記事では、すららならではの特徴や強みについて詳しく紹介していきます。
特に、学習のサポート体制や、不登校・発達障害への対応といった点で、すららが選ばれている理由をチェックしてみましょう。
メリット1・対人サポート付き!「すららコーチ」がある
オンライン学習は、基本的に「自分で進める」スタイルが多いため、途中で挫折してしまったり、勉強の進め方に迷ったりすることがあります。
しかし、すららには「すららコーチ」という学習サポートのプロがついているため、安心して学習を続けることができます。
他の家庭用タブレット教材にはない、大きなメリットの一つです。
すららはプロの学習コーチが進捗を管理してくれる
すららコーチは、子ども一人ひとりの学習進捗をしっかり管理し、適切なアドバイスを提供してくれます。
「この単元が苦手だから復習しよう」「このペースなら○日で目標達成できる」といった具体的な指示がもらえるため、学習計画を立てるのが苦手な子どもでも無理なく続けられます。
学習の進み具合をチェックし、必要に応じて軌道修正もしてくれるので、計画倒れにならずに学習を継続できるのがポイントです。
コーチが学習スケジュールを子どもに合わせて作成してくれる
すららコーチは、子どもの理解度や生活リズムに合わせた学習スケジュールを作成してくれます。
「部活が忙しくて勉強の時間が取れない」「苦手な科目はゆっくり進めたい」といった個々の事情に応じたプランを立てられるため、無理のないペースで学習を進められます。
親がスケジュール管理をする手間も省けるため、共働き家庭や忙しい親御さんにも大きなメリットがあります。
メリット2・不登校・発達障害対応に特化している
すららは、不登校や発達障害の子どもにも対応できる学習教材として、多くの学校や教育機関で採用されています。
「学校に行けないけど、勉強は続けたい」「発達障害の特性に合った学習方法を探している」という家庭にとって、安心して取り組めるサポートが整っています。
不登校や発達障害の子向けに、文科省推薦教材として採用されてる実績がある
すららは、文部科学省が推奨するオンライン学習教材として、多くの自治体や学校で導入されています。
通常の学校の授業が受けられない子どもたちでも、すららを活用することで学習を継続できる環境が整えられています。
特に、不登校や発達障害のある子どもに向けた配慮がされている点が高く評価されています。
不登校児童に対して「出席扱い」される学校も多い
すららを活用した学習は、一部の学校では「出席扱い」と認められることがあります。
これは、文部科学省の方針により、適切な学習環境が確保されている場合、不登校の子どもでも在宅学習が出席として認められるケースがあるためです。
すららを導入することで、学校の授業に参加しなくても学習の遅れを取り戻せるだけでなく、正式に出席としてカウントされる可能性があるのは大きなメリットです。
ASD・ADHD・LD(学習障害)に合わせたカリキュラム&サポートが受けられる
発達障害のある子どもにとって、一般的な学習方法では理解しにくい場合があります。
すららでは、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)、LD(学習障害)など、それぞれの特性に配慮したカリキュラムとサポートを提供しています。
たとえば、「集中力が続かない子どもには短時間で学べるプログラムを用意」「視覚的な説明が理解しやすい子にはアニメーションを活用」といった工夫がされています。
これにより、自分の特性に合った学習方法で、無理なく勉強を続けることができます。
メリット3・学年を超えた「無学年学習」ができる
すららの大きな特徴の一つが「無学年学習」です。
通常の学校教育では、学年ごとに決められたカリキュラムに沿って学習が進みますが、すららでは学年にとらわれることなく、自由にさかのぼり学習や先取り学習ができます。
これにより、子ども一人ひとりの理解度に応じた柔軟な学習が可能になります。
学年関係なく自由にさかのぼり・先取りできる
すららの無学年学習では、学年に関係なく、自分に必要なレベルの学習を進めることができます。
例えば、小学5年生が中学数学にチャレンジすることも可能ですし、中学生が小学校の算数を復習することもできます。
「この単元がわからないから戻って学習したい」「もっと難しい内容にチャレンジしたい」といったニーズに柔軟に対応できるのが、すららの強みです。
発達障害の子は「つまずいたまま進まない」からマイペースに進められるのはポイント
発達障害のある子どもにとって、学校の授業のペースについていくことが難しいケースがあります。
すららなら、「理解できないまま次の単元へ進んでしまう」という状況を防ぎ、つまずいた部分をしっかり復習してから次へ進むことができます。
また、先取り学習も可能なので、得意な科目はどんどん進めることができるのもメリットです。
マイペースに学習できることで、無理なく自信をつけながら勉強を続けることができます。
メリット4・AI診断×対人コーチングで学習設計が精密
すららでは、AIを活用した学習診断と、すららコーチによる対人サポートを組み合わせた「Wサポート体制」が整っています。
AIによる自動解析だけでなく、人間のコーチが子どもの学習状況を細かくチェックしながら調整してくれるため、一人ひとりに最適な学習プランを提供できるのが大きな特徴です。
AI+人間コーチのWサポートはすららだけのポイント
オンライン学習サービスの多くは、AIによる学習サポートのみを提供しています。
しかし、すららではAIの診断結果をもとに、すららコーチが学習計画を調整し、より個別に最適化された学習ができるようになっています。
AIのデータ分析と人間のサポートが組み合わさることで、より効果的な学習設計が可能になります。
AIだけではフォローしきれない細かい学習状況を、コーチが調整してくれる
AIは膨大なデータをもとに学習の進捗を分析し、適切な問題を出題してくれますが、子どもの体調や気分、モチベーションの変化といった「人間的な要素」までは判断できません。
すららコーチがついていることで、「今日は集中力が続かないから学習量を調整しよう」「この単元が苦手だから、もっと復習が必要」といった細かい調整が可能になります。
こうした対人サポートがあることで、子どもが途中で挫折せず、継続的に学習できる環境が整います。
メリット5・紙を使わず、すべてデジタルでも「記述力」が鍛えられる
オンライン学習の多くは「選択式」の問題が中心で、記述力を鍛えるのが難しいことが課題です。
しかし、すららではデジタル教材でありながら、「論理的に書く力」や「説明する力」を育てるカリキュラムが用意されているため、紙の学習に近い形で記述力を養うことができます。
デジタル学習でもしっかり文章を書く力を伸ばせるのが、すららの大きな特徴です。
「論理的に書く力」「説明する力」にフォーカスしたカリキュラム
すららの国語のカリキュラムでは、単に正解を選ぶだけでなく、考えを言語化するトレーニングが組み込まれています。
例えば、「文章の要約」「意見を書く練習」「説明文を作成する問題」などを通じて、自分の考えを整理しながら書く力を養うことができます。
論理的な文章力は、受験や将来の仕事にも役立つため、すららのこうした学習スタイルは大きなメリットです。
読解+記述のトレーニングがデジタル完結でできる教材は珍しい
多くのデジタル教材では、読解力を養う問題はあっても、実際に「書く」練習まで対応しているものは少ないです。
しかし、すららでは文章の要約や記述問題に対応しており、すべてデジタル環境でトレーニングを行うことができます。
特に、「紙に書くのが苦手な子」「漢字や文章を書くのに抵抗がある子」にとって、タブレットやPC上で記述の練習ができるのは大きな利点です。
メリット6・途中でやめても「再開」がしやすい
オンライン学習を継続するうえで、「一度やめたら復帰しにくい」という問題がよくあります。
しかし、すららでは途中で学習を中断しても、簡単に再開できる仕組みが整っています。
不登校の子どもや、体調の波がある子どもにとって、自由に休んでまた学習を始められる環境はとても重要です。
すららは一時中断→復帰が簡単にできる
すららは、途中で学習をやめても、再開する際に「どこまで進んでいたのか」「どこが苦手だったのか」をAIが記録してくれます。
そのため、「久しぶりに学習を再開したら、どこからやればいいかわからない」といった不安がなく、スムーズに学び直しができます。
学校の授業のように、一度休むとついていけなくなるという心配がないのがポイントです。
不登校や発達障害の子は「学習ペースに波がある」から、自由に休んで戻れる環境は重要
不登校や発達障害のある子どもは、学習ペースに波があることが少なくありません。
「今日は勉強に集中できるけど、明日はできない」といった状況もあります。
そのため、「毎日決まった量を必ずこなさなければならない」という学習スタイルは、プレッシャーになりがちです。
すららなら、体調や気分に合わせて自由に学習を進めることができるため、無理なく続けられる環境が整っています。
メリット7・出席認定・教育委員会との連携実績がある
すららは、ただのオンライン教材ではなく、教育委員会や学校と連携しながら、不登校支援にも力を入れています。
実際に、すららを活用することで「出席扱い」と認められる学校も増えており、正式な学習ツールとしての実績を持っているのが特徴です。
すららを使っていると「出席扱い」として学校が認めるケースが多数
すららを活用した学習は、一部の学校では「出席扱い」として認められています。
これは、すららのカリキュラムが文部科学省の学習指導要領に準拠しており、学校の授業と同等の学習効果があると判断されているためです。
不登校の子どもにとって、「学校に行けなくても学習を継続できる」という安心感があるのは、大きなメリットになります。
不登校支援教材として、学校や病院と連携しているのはすららならでは
すららは、教育機関だけでなく、病院や支援施設とも連携しながら、不登校や長期療養中の子どもの学習サポートを行っています。
例えば、学校に通えない子どもが、すららを通じて学習を進めることで、学校復帰の準備を整えたり、学習の遅れを防いだりすることができます。
このような支援体制が整っているのは、すららならではの大きな強みです。

【すらら】はうざいと言われる原因は?すららのデメリットについて紹介します
すららは、多くの家庭で評価されているオンライン学習教材ですが、一部では「うざい」と感じる声があるのも事実です。
これは、すららのサポート体制や学習システムの特徴が、すべての子どもに合うわけではないからです。
どんな教材にもメリット・デメリットがあり、向き不向きがあるものです。
この記事では、すららのデメリットと、「うざい」と言われる理由について詳しく解説します。
原因1・すららコーチやサポートからの連絡がしつこいと感じることがある
すららでは、学習をしっかりサポートするために「すららコーチ」という学習指導者がつき、定期的に連絡をしてくれます。
これにより、計画的に勉強を進めやすくなるメリットがありますが、一方で「頻繁に連絡がくるのが面倒」と感じる子どもや親もいるようです。
自主的にやりたい子や、放っておいてほしい子には合わないこともある
すららコーチは、子どもの学習状況をしっかり見守り、適切なアドバイスをしてくれます。
しかし、「自分のペースで自由に学習したい」「過干渉されるのが苦手」というタイプの子どもにとっては、サポートがかえってストレスになってしまうことがあります。
特に、「自分で計画を立てて勉強できる」「あまり干渉されたくない」という子どもにとっては、サポートが「うざい」と感じられる原因になることもあるようです。
原因2・「やらされ感」が強くなるとプレッシャーに感じることがある
すららでは、AIが自動で学習計画を作成し、子どもが無理なく進められるようにサポートしてくれます。
しかし、これが逆に「決められたスケジュールに縛られている」と感じてしまう子どももいます。
勉強が苦手な子や、マイペースに進めたい子にとっては、プレッシャーになることがあるようです。
自動で学習計画を作ってくれるAIに縛られていると感じてしまうことがある
AIが学習状況を分析し、適切な問題を提示してくれるのはすららの強みですが、「今日は気分が乗らない」「今は別の単元を勉強したい」と思ったときに、計画通りに進めなければならないのがストレスになることもあります。
また、計画通りに進まないと「遅れている」という意識が生まれ、焦りやプレッシャーを感じることも。
学習習慣がしっかりついている子には便利な機能ですが、自由に勉強を進めたいタイプの子どもには合わない可能性があります。
原因3・キャラクターやナビゲーションが子どもっぽい・くどいと感じることがある
すららの授業は、アニメーションキャラクターがナビゲートしてくれる対話型授業になっています。
小学生には楽しく学べる工夫がされている一方で、高学年や思春期の子どもには「キャラクターの口調がくどい」「幼稚っぽく感じる」と思われることがあるようです。
高学年や思春期の子にはキャラクターがうざいと感じることがある
すららの授業は、先生役のキャラクターが子どもと会話をしながら進めていきます。
小学生のうちは楽しく学習できる工夫としてメリットになりますが、中学生や高校生になると「キャラが話しすぎてテンポが悪い」「説明がまどろっこしい」と感じることがあるかもしれません。
特に、シンプルな学習を求めている子にとっては、キャラクターの会話が「くどい」と思われることもあり、相性が分かれるポイントです。
原因4・勧誘や営業の印象が「しつこい」と感じる人がいる
すららは、オンライン学習教材の中でも知名度が高いため、SNS広告やWebサイトでのプロモーションを頻繁に行っています。
また、資料請求や無料体験を申し込むと、その後のフォロー連絡が比較的多いと感じる人もいるようです。
これが一部のユーザーには「勧誘がしつこい」「営業っぽい」と捉えられることがあります。
「連絡が頻繁」と感じると、SNSでは「うざい」と言われることがある
すららは、学習を継続してもらうために、無料体験後や資料請求後にフォローの連絡をしてくれることがあります。
しかし、人によっては「頻繁に連絡が来るのが嫌」「もっとゆっくり検討したいのに…」と感じてしまうことも。
そのため、SNSなどでは「しつこい」との声が出ることもあります。
しつこい勧誘が嫌な場合は、初回の連絡時に「検討中なので、しばらく連絡を控えてほしい」と伝えておくのも一つの方法です。
原因5・料金が高く感じる割に効果が実感できない場合がある
すららの料金は、一般的なタブレット学習教材と比べるとやや高めに設定されています。
手厚いサポートや無学年学習ができる点では価値がありますが、「子どもがうまく活用できなかった」「期待していたほど成果が出なかった」という場合、保護者が「料金に見合わない」と感じることもあるようです。
子供が1人で学習に取り組めないままだと勉強効果を実感できない保護者もいる
すららは、すららコーチのサポートやAI分析など、多機能な学習システムを備えていますが、最終的には「子どもが自分で学習に取り組めるかどうか」が鍵になります。
特に、勉強習慣がない子どもが「最初から1人で取り組むのは難しい」と感じた場合、親のサポートが必要になることも。
親が積極的に学習管理をする前提で始めたわけではない家庭では、「結局、親が関与しないと続かない」と感じてしまい、効果が実感できないこともあるようです。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは高い?すららの料金プランについて紹介します
すららは、無学年式の学習システムや手厚いサポートが特徴の家庭用タブレット教材です。
しかし、他のタブレット学習サービスと比較すると、やや高めの料金設定になっています。
そのため、「すららは高い?」と感じる方もいるかもしれません。
ここでは、すららの料金プランを詳しく紹介し、実際のコストについて解説します。
すらら家庭用タブレット教材の入学金について
すららを利用する際には、月額料金とは別に入学金が必要です。
コースによって入学金の金額が異なるので、以下の表で確認しておきましょう。
| コース名 | 入学金(税込) |
| 小中・中高5教科コース | 7,700円 |
| 小中・中高3教科、小学4教科コース | 11,000円 |
すらら家庭用タブレット教材/3教科(国・数・英)コース月額料金について
すららの3教科コース(国語・数学・英語)は、小中コース・中高コース共に同じ料金設定になっています。
毎月支払いと4ヵ月継続コースでは月額料金が異なるので、少しでも費用を抑えたい方は4ヵ月継続コースを選ぶと良いでしょう。
毎月支払いコースの料金
| コース名 | 月額 |
| 小中コース | 8,800円 |
| 中高コース | 8,800円 |
4ヵ月継続コースの料金
| コース名 | 月額 |
| 【4ヵ月】小中コース | 8,228円 |
| 【4ヵ月】中高コース | 8,228円 |
すらら家庭用タブレット教材/4教科(国・数・理・社)コース月額料金について
4教科(国語・数学・理科・社会)を学べるコースも用意されています。
こちらも、毎月支払いコースと4ヵ月継続コースで料金が異なるため、継続予定の方は4ヵ月コースを選ぶと割引価格で利用できます。
| コース名 | 月額 |
| 小学コース(毎月支払いコース) | 8,800円 |
| 小中コース(4ヵ月継続コース) | 8,228円 |
すらら家庭用タブレット教材/5教科(国・数・理・社・英)コース月額料金について
5教科(国語・数学・理科・社会・英語)がすべて学べるフルコースも用意されています。
特に、受験を控えているお子さんには、総合的に学習できる5教科コースが便利です。
毎月支払いコースの料金
| コース名 | 月額 |
| 小学コース | 10,978円 |
| 中高コース | 10,978円 |
4ヵ月継続コースの料金
| コース名 | 月額 |
| 【4ヵ月】小中コース | 10,428円 |
| 【4ヵ月】中高コース | 10,428円 |
すららは、料金だけを見ると「高い」と感じるかもしれませんが、その分、無学年式の学習やAIサポート、すららコーチによるフォローが充実しているのが特徴です。
特に、学校の授業についていけないお子さんや、発達障害・不登校の子どもにとっては、通常のタブレット学習よりも手厚い支援が受けられるメリットがあります。
費用対効果を考えながら、自分に合ったプランを選ぶことが大切ですね。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの勉強効率や勉強効果は?コースについて紹介します
すららは、オンライン学習の中でも「無学年式」「AIサポート」「対話型授業」など独自の特徴を持った教材です。
しかし、実際にどれくらい勉強の効率が上がるのか、どんな効果があるのか気になる方も多いのではないでしょうか?ここでは、すららの3教科コース(国語・数学・英語)に注目し、その勉強効果について詳しく紹介していきます。
すらら3教科コース(国・数・英語)の勉強効果について紹介します
すららの3教科コースは、国語・数学・英語を重点的に学べるカリキュラムです。
特に、主要3教科は学校の成績にも大きく影響するため、「テストの点数を上げたい」「内申点を上げたい」と考えている方にはおすすめのコースです。
ここでは、すららの3教科コースを活用することで期待できる勉強効果について紹介します。
勉強効果1・基礎力の定着がとにかく早い
すららの学習スタイルは、無学年式を採用しているため、学年を超えて自由に学習を進めることができます。
そのため、「前の学年の内容が理解できていないまま進んでしまった…」という心配がなく、基礎力の定着をスムーズに行うことができます。
特に、数学や英語は「積み重ねが大切な科目」と言われるように、過去の学習内容がしっかり身についていないと、次の単元を理解するのが難しくなります。
すららなら、分からない単元まで戻ってじっくり復習できるため、苦手を克服しながら学習を進めることができます。
勉強効果2・短時間で「できる→わかる→応用」の流れを作ってくれる
すららでは、学習の流れとして「まず解いてみる→解説を聞く→類似問題で定着させる」というステップが組まれています。
このため、単に問題を解くだけではなく、理解を深めながら応用問題にも挑戦できるようになります。
特に、数学や英語はパターンを覚えるだけでなく、「なぜそうなるのか?」を理解することが重要です。
すららでは、アニメーションを活用した解説や、対話型の授業によって、視覚的にも理解しやすい環境が整っています。
短時間でも効率よく学べるため、「勉強時間が確保しにくい」「集中力が続かない」といった悩みを抱えるお子さんにもぴったりです。
勉強効果3・中学生は主要3教科で内申点が決まるから「点数を上げたい」「定期テストで成果を出したい」という目的に直結する
中学生の場合、内申点を決めるうえで特に重要なのが「国語・数学・英語」の3教科です。
これらの教科は、高校受験にも直結するため、早いうちからしっかりと成績を上げておくことが大切です。
すららでは、定期テスト対策として、過去の単元をさかのぼって復習したり、間違えた問題をAIが分析して重点的に出題してくれたりするため、テストに向けた効率的な学習が可能です。
「点数を上げたい」「テストで成果を出したい」と考えている中学生にとって、すららの3教科コースは非常に実用的な学習ツールとなるでしょう。
すらら4教科コース(国・数・英語・理科または社会)の勉強効果について紹介します
すららの4教科コースでは、主要3教科(国語・数学・英語)に加え、理科または社会を学ぶことができます。
理科・社会は暗記科目と思われがちですが、単に覚えるだけではなく、理解を深めることで成績アップにつながります。
すららでは、効率よく学習できる仕組みが整っているため、学校の授業よりも短時間で効果的に学ぶことが可能です。
ここでは、すららの4教科コースを活用することで得られる勉強効果について紹介します。
勉強効果1・理科・社会は、「繰り返し学習」と「確認テスト」で記憶の定着率が高まる
すららでは、学んだ内容を定着させるために「繰り返し学習」と「確認テスト」を組み合わせた学習法が採用されています。
理科・社会は、用語や現象を理解することが重要ですが、学校の授業では「一度習ったら終わり」になりがちです。
しかし、すららではAIが学習の進捗を分析し、苦手な部分を重点的に出題してくれるため、忘れやすいポイントも繰り返し学ぶことができます。
確認テストによって「どこが理解できていないのか」をチェックしながら進められるため、記憶の定着率が高まるのが特徴です。
勉強効果2・ポイントを押さえた要点学習で、時間対効果がとてもいい
すららの理科・社会のカリキュラムは、長時間勉強しなくても効率よく要点を押さえられるように設計されています。
例えば、歴史の流れをアニメーションで視覚的に学んだり、地理のポイントを対話形式で整理したりすることで、短時間でも理解しやすくなっています。
また、理科の実験や現象を映像で学ぶことで、教科書の説明だけではイメージしにくい内容もスムーズに理解できます。
このように、すららでは、重要なポイントをわかりやすく整理しながら学習できるため、限られた時間でもしっかり知識を身につけることができます。
勉強効果3・通常の塾や学校より、短時間で理解→テスト対策ができるところが強み
学校の授業では、限られた時間内で多くの単元をカバーする必要があるため、「なんとなく理解したけど、テストでは解けない」ということが起こりがちです。
しかし、すららでは、学習内容をコンパクトにまとめながら、必要な知識をしっかり身につけられるように工夫されています。
また、AIが苦手分野を自動的に分析し、最適な問題を出題してくれるため、「どこを重点的に勉強すればいいのかわからない」という悩みも解消されます。
このように、短時間で効率的に学習できることが、すららの大きな強みのひとつです。
すらら5教科コース(国・数・英語・理科・社会)の勉強効果について紹介します
すららの5教科コースは、主要3教科(国語・数学・英語)に加えて、理科・社会まで幅広く学べる総合的な学習プランです。
特に、中学生の内申点や高校受験を意識した学習をしたい方にとって、バランスよく学べるこのコースは大きなメリットがあります。
ここでは、すららの5教科コースを活用することで期待できる勉強効果について詳しく紹介します。
勉強効果1・全教科を満遍なくカバーし、内申点・通知表UPに直結 / 特に中学生の内申点は「5教科バランス型」が必須
中学生の通知表(内申点)は、高校受験の合否に大きく影響します。
そのため、特定の科目だけではなく、5教科すべての成績をバランスよく伸ばしていくことが重要です。
すららの5教科コースでは、主要科目の基礎学習はもちろん、理科・社会の重要ポイントを効率よく学べるため、「苦手な教科が足を引っ張る…」といった状況を防ぐことができます。
また、AIが苦手な分野を特定し、集中的に学習できるため、効率よく成績アップを目指せるのが特徴です。
勉強効果2・高校受験にも直結する実力アップ / 模試や過去問対策にも応用できる
高校受験では、5教科すべてが試験範囲となるため、まんべんなく学習しておくことが重要です。
すららの5教科コースでは、学校の授業に合わせた学習だけでなく、模試や過去問対策にも活かせる内容が含まれています。
また、無学年式の学習システムを活用すれば、「前の学年の復習が必要」「入試に向けて先取り学習をしたい」といったニーズにも柔軟に対応できます。
入試の基礎固めから応用問題対策まで、自分のペースで取り組めるため、高校受験に向けてしっかりと実力をつけたい方に最適なコースです。
勉強効果3・5教科すべてAIが自動で弱点を分析し、学習計画を立ててくれるから効率的
すららでは、AIを活用した学習サポートがあるため、苦手な教科や単元を自動的に分析し、必要な学習計画を提案してくれます。
「どこがわからないのか」「どの範囲を重点的に復習すべきか」といった悩みを解消し、効率よく学習を進めることができます。
通常、5教科すべてをまんべんなく勉強しようとすると、計画を立てるのが難しくなりがちですが、すららなら「自分のペースで必要な学習だけを集中して進められる」ため、短時間でも効果的に学ぶことができます。
勉強効果4・他の教材や塾より、時間あたりの学習効果は高いと感じる人が多い
塾や学校の授業は決められた時間に沿って進められるため、「苦手な部分をもう少し復習したい」「得意な教科をもっと先に進めたい」と思っても自由に調整することが難しい場合があります。
一方、すららは自分の理解度に合わせて進められるため、無駄な時間が少なく、短時間で効率的に学習できるのが特徴です。
また、アニメーションを使った解説や、対話形式の授業があるため、「ただ問題を解くだけ」ではなく、しっかりと理解を深めながら学習を進められます。
そのため、他の教材や塾よりも「短い時間でしっかりと学習できる」と感じる人が多いのも、すららの強みのひとつです。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは発達障害や不登校でも安心・安全に使える理由
すららは、一般的なタブレット学習とは異なり、発達障害のある子どもや不登校の子どもにも適した学習環境を提供しています。
学校の授業についていくのが難しい場合や、人とのコミュニケーションが苦手な子どもでも、自分のペースで無理なく学べる工夫がされています。
無学年式の学習システムや、感情的なプレッシャーを感じにくい設計がされているため、安心して勉強に取り組めるのが特徴です。
ここでは、すららが発達障害や不登校の子どもにとって「安全に使える理由」について詳しく紹介します。
安全な理由1・「本人のペースで学習できる」からプレッシャーがない
すららは、学年の枠にとらわれない無学年式の学習を採用しているため、学校の授業の進度に関係なく、本人の理解度に合わせた学習ができます。
学校では、クラスの進度に合わせなければならないため、「授業についていけない」「もう少しじっくり学びたいのに進んでしまう」といったストレスを感じることがあります。
しかし、すららなら「得意な科目は先に進み、苦手な科目は戻って学ぶ」といった柔軟な学習スタイルが可能です。
学校の授業の「遅れ」や「先取り」を気にせず、マイペースに学べるから、ストレスが少ない
発達障害や不登校の子どもにとって、学校の授業のペースについていくことは大きな負担になることがあります。
すららなら、学習を中断したとしても、再開したときに「授業に遅れている」というプレッシャーを感じることなく、自分のペースで進められます。
また、得意な教科はどんどん先に進めることができるため、「勉強が楽しい」と感じやすくなります。
こうした自由度の高さが、すららがストレスなく学べる理由の一つです。
ADHDタイプの子は「集中できる時に一気に」、ASDタイプの子は「毎日決まったペースで」、それぞれに合った使い方ができる
発達障害にはさまざまなタイプがあり、学習スタイルも個々に異なります。
ADHD(注意欠陥・多動性障害)の子どもは、集中力が持続しにくいことが多いため、気分が乗ったときに一気に進める方が効率的です。
一方、ASD(自閉スペクトラム症)の子どもは、決まったルーチンで学習を進める方が安心感を持てることが多いです。
すららなら、どちらのタイプにも対応できる柔軟な学習スタイルを選ぶことができるため、それぞれの特性に合った学び方ができます。
安全な理由2・「対面の緊張や不安がゼロ」だから取り組みやすい
学校の授業や塾のように、先生やクラスメイトと対面でやり取りをすることが苦手な子どもにとって、すららのアニメーション学習は大きな安心感を与えてくれます。
先生との対話やクラスメイトの目を気にせず、自分のペースで学べるため、学習に対するハードルを下げることができます。
アニメーションのキャラが優しく教えてくれて、正解でも不正解でも感情的な反応をされることはない
すららでは、アニメーションのキャラクターが先生役となり、対話形式で授業を進めてくれます。
これにより、間違えたときに「怒られるのでは?」という不安を感じることなく、リラックスして学習に取り組めます。
また、正解・不正解に関係なく、キャラクターが優しくフィードバックしてくれるため、自信を失うことなく学習を続けられます。
人間の先生だと、どうしても感情が入ることがありますが、すららのキャラクターなら感情的な反応がなく、安心して学べるのがメリットです。
人とのコミュニケーションに不安がないから安心して学ぶことができる
発達障害のある子どもの中には、対面でのコミュニケーションに不安を感じる子も少なくありません。
学校の授業では、「発言しなければいけない」「グループ活動がある」といったプレッシャーを感じることがあります。
しかし、すららはオンライン学習なので、人と直接コミュニケーションを取る必要がなく、落ち着いて勉強することができます。
学習内容に集中できる環境が整っているため、対人ストレスを感じずに学習を進められるのが大きな利点です。
すららは、発達障害や不登校の子どもにとって、安心して学べる工夫がたくさん詰まった教材です。
本人のペースで学べること、対人のプレッシャーがないこと、そしてアニメーションを活用した優しい学習スタイルが、ストレスなく勉強を続けられる理由です。
「学校の授業が合わない」「対人ストレスなく勉強したい」と感じている方には、すららは最適な学習ツールといえるでしょう。
安全な理由3・発達障害に対応した「ユニバーサルデザイン」設計
すららは、発達障害のある子どもや、学習に困難を感じる子どもでも無理なく取り組めるよう、ユニバーサルデザインを採用しています。
ユニバーサルデザインとは、「誰にとっても使いやすく、わかりやすい設計」を意味し、すららでは「視覚的な理解を助ける工夫」「音声を活用した学習」「つまずきを防ぐ学習サポート」などが組み込まれています。
これにより、発達障害の特性に関係なく、自分に合った学習方法で無理なく続けることができます。
すららは「誰でも理解しやすく、つまずきにくい」ように作られている
すららは、教科書やプリントのように「文章を読むだけ」の学習ではなく、アニメーションや音声を活用することで、理解しやすい工夫がされています。
特に、学習につまずきやすいポイントでは、視覚的に理解しやすい図解や、わかりやすい言葉での解説があるため、「難しい内容でもスムーズに理解できる」というメリットがあります。
また、一つの問題に対して複数のアプローチが用意されており、「一度で理解できなかったら、別の方法で学び直せる」点も特徴的です。
これにより、学習の苦手意識を持ちにくくなり、続けやすくなっています。
読字障害(ディスレクシア)、言語理解に時間がかかるASDの子にも分かりやすい
発達障害の中でも、ディスレクシア(読字障害)を持つ子どもは、文章を読むのに時間がかかり、学習がスムーズに進まないことがあります。
すららでは、音声での解説が充実しているため、文字を読むのが苦手な子でも、聞きながら学習を進めることができます。
また、ASD(自閉スペクトラム症)の子どもは、言葉の意味を理解するのに時間がかかることがありますが、すららでは「具体的な例」や「視覚的な説明」を多用しているため、よりわかりやすくなっています。
「読めない」「意味がわからない」という学習の壁を減らすことで、よりスムーズに学習に取り組むことができるのが特徴です。
「視覚優位」「聴覚優位」どちらのタイプの子にもマッチしやすいのが特長
発達障害のある子どもの中には、「視覚優位(目で見て理解しやすい)」タイプと「聴覚優位(耳で聞いて理解しやすい)」タイプがいます。
すららでは、どちらのタイプにも対応できるように、映像・音声・文字のすべてを活用した学習方法が採用されています。
例えば、視覚優位の子には「アニメーションや図解での説明」が有効であり、聴覚優位の子には「ナレーションによる音声解説」が役立ちます。
こうした多様な学習スタイルを取り入れることで、それぞれの子どもに合った学び方ができるようになっています。
「音声速度」を調整できる機能もあるから、「ゆっくり聞きたい」「早く進めたい」など、子どもの特性に合わせられる
すららでは、音声の速度を調整できる機能が搭載されているため、学習のペースを子どもに合わせて調整することができます。
例えば、「じっくり聞きながら理解したい」という子どもには音声をゆっくり再生することができ、「理解できたから早く進めたい」という場合にはスピードを上げることも可能です。
発達障害のある子どもは、情報処理のスピードに個人差があるため、自分に合った速さで学べるのは大きなメリットです。
また、一度聞いただけでは理解しにくい場合も、何度でも繰り返し再生できるため、学習の定着を助ける役割も果たします。
すららは、発達障害のある子どもや、学習に苦手意識を持っている子どもでも使いやすいように、さまざまな工夫がされています。
ユニバーサルデザインを取り入れた設計により、「理解しやすい」「つまずきにくい」環境を提供することで、子どもが自信を持って学習に取り組めるようになっています。
発達障害の特性に応じた学び方ができるため、安心して続けられるのがすららの大きな魅力です。
安全な理由4・間違えても怒られない・恥をかかない設計
発達障害のある子どもや、不登校の子どもにとって、「間違えたときの対応」は学習への意欲に大きく影響します。
学校や塾では、先生や周囲の友達に間違いを指摘されることがあり、「恥ずかしい」「できない自分が嫌だ」と感じてしまうことがあります。
その結果、学習に対して消極的になったり、自信を失ったりしてしまうこともあります。
しかし、すららでは、間違えることを前提とした学習設計になっているため、ミスをしてもネガティブな感情を抱きにくく、安心して学習を続けることができます。
「否定」ではなく「納得」させてくれるから、自己肯定感が下がりにくい
すららでは、問題を間違えたときに「ダメ」「違う」といった否定的な言葉は使われません。
その代わりに、「ここがポイントだったね」「もう一度考えてみよう」と、間違いの原因を丁寧に解説しながら、納得しやすい形でフィードバックが行われます。
これは、発達障害のある子どもにとって特に重要な要素であり、「否定されるとやる気がなくなる」「間違えるのが怖くてチャレンジできない」といった不安を軽減する効果があります。
正解を導き出すプロセスを大切にすることで、学習をポジティブな体験に変えることができます。
学校や塾では感じがちな「恥ずかしい」「できない」といったネガティブ感情を抱きにくい
学校や塾の授業では、先生の前やクラスメイトの前で答えを発表する場面があり、間違えると「恥ずかしい」と感じることがあります。
特に、周囲の目を気にしやすいASD(自閉スペクトラム症)の子どもにとっては、こうした状況がストレスになることがあります。
しかし、すららでは、一人で学習する環境が整っているため、「間違えても誰にも見られない」「自分のペースでやり直せる」という安心感があります。
その結果、学習に対するプレッシャーが少なくなり、リラックスして取り組めるようになります。
安全な理由5・「ゲーム感覚」の楽しい仕組みで続けやすい
学習を継続するには、「楽しい」と感じられることが重要です。
すららでは、アニメキャラクターが学習をナビゲートし、クイズ形式の問題やゲーム感覚の要素を取り入れることで、「もうちょっと続けたい」と思えるような仕組みが整っています。
特に、飽きやすいADHD(注意欠陥・多動性障害)の子どもにとっては、単調な学習よりも「すぐに結果が出る」「達成感を味わえる」といった要素があるほうが、モチベーションを維持しやすい傾向があります。
アニメキャラクターがナビゲートし、クイズ形式やゲーム感覚の要素があるから「もうちょっと続けたい」と思わせる工夫がされてる
すららの授業は、アニメーションのキャラクターが先生役となり、対話形式で進行します。
これにより、単調な学習にならず、まるでストーリーを楽しんでいるような感覚で勉強を進めることができます。
また、問題がクイズ形式になっているため、ゲームのような感覚で取り組むことができ、「あと少しやってみよう」「次は正解できるかな」と自然に学習を続けたくなる仕組みになっています。
こうした楽しい学習環境が、継続のしやすさにつながります。
ADHDの子は「すぐに褒められる」「すぐに結果が出る」とやる気が続きやすい傾向がある
ADHDの子どもは、長時間の集中が難しいことが多く、学習の途中で飽きてしまうことがあります。
しかし、すららでは「問題を解くとすぐにフィードバックがもらえる」「正解するとキャラクターが褒めてくれる」といった仕組みがあり、短いサイクルで達成感を得ることができます。
これにより、「やればできる」「もっとやってみよう」という前向きな気持ちを引き出し、学習の継続につながります。
すららの「ゲーム感覚の学習」と「間違えても怒られない設計」は、発達障害の子どもや不登校の子どもにとって、安心して学べる環境を提供しています。
学習に対するプレッシャーを減らし、楽しみながら続けられる仕組みが整っているため、学ぶことに対する前向きな気持ちを育てることができます。
安全な理由6・「すららコーチ」がいるから親子で抱え込まなくていい
発達障害のある子どもや、不登校の子どもが学習を続けるためには、親のサポートが欠かせません。
しかし、家庭学習をすべて親が管理するのは大きな負担になりますし、親子間で学習のことで衝突することもあります。
すららでは、「すららコーチ」という専門の学習サポーターがつくため、親子だけで学習を抱え込む必要がなくなります。
コーチが適切なサポートを行うことで、子どもが無理なく学習を続けられる環境を整えることができます。
ADHDやASD、学習障害の特性を理解した対応をしてくれるコーチが多い
すららコーチの大きな特徴の一つは、発達障害の特性を理解した対応をしてくれることです。
たとえば、ADHDの子どもには「短時間でも達成感を感じられる学習計画」、ASDの子どもには「毎日決まった流れで学べるスケジュール」、学習障害のある子どもには「苦手な部分を丁寧にフォローする学習方法」といった具合に、それぞれの特性に合わせたアドバイスをしてくれます。
このような対応があることで、親がすべてを考えなくても、子どもに合った学習方法を見つけることができます。
コーチが学習計画を立てたり、つまずきポイントを教えてくれる
学習の進め方がわからないと、「何から手をつければいいのか」「どのペースでやればいいのか」と迷ってしまい、学習が進まなくなることがあります。
すららコーチは、子どもの理解度やペースに合わせた学習計画を立て、進捗を確認しながら適切なアドバイスをしてくれます。
特に、つまずきやすいポイントを事前に把握し、「ここを復習するといいよ」と具体的にサポートしてくれるため、効率よく学習を進めることができます。
親が学習管理をしなくても、コーチがフォローしてくれるので、親の負担が大きく軽減されるのも魅力です。
安全な理由7・「完全オンライン」だから家で完結できる
すららは、すべての学習がオンラインで完結するため、通塾の必要がありません。
不登校の子どもや、発達障害の特性から外出が苦手な子どもでも、安心して自宅で学習を続けることができます。
学校に行けない間も、学習の遅れを最小限に抑えられるので、子ども自身の自信を保つことにもつながります。
タブレット1台あればできるから、環境づくりもシンプルだし、親の負担も減る
オンライン学習のメリットは、学習環境の準備がシンプルなことです。
すららはタブレットやパソコンが1台あれば、すぐに学習を始めることができます。
塾のように送り迎えの必要もなく、学習教材を毎回準備する手間もありません。
特に、発達障害のある子どもは、環境の変化にストレスを感じやすいため、自宅で学習できることは大きなメリットになります。
親も、「今日は塾に連れて行かないと」「宿題をやらせなきゃ」といった負担が減り、子どもとの関係を穏やかに保つことができます。
通学できない間も学習の「穴」を作らず、自信を持たせてあげられる
不登校の子どもが最も不安に感じることの一つは、「学習の遅れ」です。
「学校に行けていないから、勉強が遅れている」「周りの子と差がついてしまう」といった焦りが、さらに学校に行きにくくなる原因にもなります。
しかし、すららなら、自宅で学校の授業と同じレベルの学習を進めることができるため、学習の遅れを最小限に抑えられます。
さらに、無学年式の学習システムなので、遅れた部分を戻って学ぶことも可能です。
「自分のペースで勉強を続けられている」という実感が、子どもの自信につながり、学習へのモチベーションを高めることにもなります。
すららの「完全オンライン学習」は、発達障害や不登校の子どもにとって、安心して学習を続けられる環境を提供してくれます。
自宅で無理なく勉強できることで、学習の遅れを防ぎながら、自信を持って成長していくことができます。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの解約・退会方法について紹介します
すららは、家庭で学べるタブレット学習教材として多くの人に利用されていますが、「子どもが続けられなかった」「他の学習方法に切り替えたい」といった理由で解約を検討する人もいます。
ただし、すららの「解約」と「退会」は意味が異なるため、手続きをする前に違いを理解しておくことが大切です。
ここでは、すららの解約・退会の方法について詳しく紹介していきます。
すららの【退会】と【解約】は意味が異なる!それぞれの違いについて解説します
すららをやめる方法には、「解約」と「退会」の2種類があります。
この2つの違いを理解しておかないと、「思っていた手続きと違った」と後悔することがあるので、注意が必要です。
すららの解約は「利用を停止すること」。毎月の支払い(利用料)を止める手続き。
解約とは、すららの利用を停止し、月額料金の支払いを止める手続きのことを指します。
解約後はすららの学習コンテンツを利用することはできなくなりますが、会員情報は残ります。
再開したい場合は、新たに契約することで再度学習を始めることができます。
子どもが一時的に学習を休みたい場合や、再開の可能性がある場合は、解約の選択肢を考えるのがよいでしょう。
すららの退会は「すららの会員そのものをやめること」。データも消える。
退会は、すららの会員そのものを辞める手続きです。
退会すると、すららに登録していたデータ(学習履歴・成績など)が完全に削除され、再開する場合もデータを引き継ぐことができません。
そのため、「もう二度とすららを利用しない」という場合にのみ、退会の手続きをするのがよいでしょう。
すららの解約方法1・すららコール(サポートセンター)に電話
すららの解約をする場合、電話での手続きが必要になります。
メールやWEBからの解約手続きは受け付けていないため、必ずすららコール(サポートセンター)に電話をかける必要があります。
| 【すららコール】0120-954-510(平日10時~20時 土日祝休み) |
すららの解約はメールやWEBからは受け付けていない
すららの解約手続きは、電話のみの対応となっています。
WEBサイトやメールでの解約手続きはできないため、注意が必要です。
「解約しようと思っていたのに、連絡するのを忘れていた」ということがないように、スケジュールを確認して早めに手続きを行うのがおすすめです。
すららの解約方法2・電話で本人確認/登録者氏名・ID・電話番号など
解約の際には、電話で本人確認が行われます。
サポートセンターのスタッフが、登録者情報を確認するため、以下の情報を用意しておくとスムーズに手続きができます。
– 登録者氏名(契約者の名前)
– すららの会員ID
– 登録している電話番号
これらの情報を事前に確認しておくと、解約手続きがスムーズに進みます。
すららの解約方法3・解約希望日を伝える/日割り計算はされません
解約を希望する場合、電話で解約希望日を伝える必要があります。
ただし、すららでは「日割り計算」が適用されないため、解約した月の途中で手続きをしても、その月の利用料金は満額請求されます。
そのため、解約のタイミングは月末に近いほうが損をしにくくなります。
解約を考えている場合は、事前に利用状況や契約期間を確認し、最適なタイミングで手続きを行うようにしましょう。
すららの解約・退会は、事前に違いを理解しておかないと「データが消えてしまった」「手続きを間違えた」といったトラブルにつながることがあります。
解約したい場合は電話での手続きが必要になるため、計画的に行うようにしましょう。
すららの退会方法について/解約手続き完了後に退会依頼をする
すららを完全にやめたい場合は、「解約」と「退会」の2つの手続きが必要になります。
解約だけでは会員情報が残るため、今後一切すららを利用する予定がない場合は、解約後に退会手続きを行う必要があります。
ただし、退会は必須ではなく、解約だけでも料金の支払いは停止されるため、そのままにしておいても問題はありません。
ここでは、すららの退会方法について詳しく解説します。
すらら解約の電話時に退会希望の旨を伝える
すららの退会を希望する場合、解約の電話をする際に「退会も希望します」と伝えることで手続きが可能です。
解約手続きが完了した後に、退会処理が行われるため、解約の時点で退会の意志を伝えておくとスムーズに進みます。
退会すると、すららの会員情報が完全に削除され、学習履歴や成績データなども消えてしまうため、今後すららを再開する可能性がある場合は、解約のみでとどめておくほうが良いでしょう。
すらら解約後に退会をしなくても全く問題はありません(料金の支払いは停止します)
すららの解約を行った後、退会をせずに会員情報を残しておくことも可能です。
解約が完了すれば、月額料金の支払いは自動的に停止されるため、退会をしなくても追加の費用は発生しません。
そのため、「しばらく休むけれど、また再開するかもしれない」「学習履歴を残しておきたい」と考えている場合は、退会せずに解約だけしておくのがおすすめです。
すららの退会は、学習履歴や登録情報が完全に削除されるため、慎重に判断することが大切です。
解約だけでも料金の支払いは止まるため、今後の利用の可能性を考慮して、適切な方法を選ぶようにしましょう。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの効果的な使い方について紹介します
すららは、家庭で学べる無学年式のタブレット教材として、多くの小学生・中学生・高校生に利用されています。
しかし、ただ使うだけでは十分な学習効果を得られないこともあります。
特に、小学生は学習習慣がまだ身についていないため、「どのように使うか」がとても重要です。
ここでは、小学生向けのすららの効果的な使い方を紹介します。
【小学生】すららの効果的な使い方について紹介します
小学生がすららを活用する際は、「継続できる学習習慣を作ること」がポイントになります。
勉強を「やらされるもの」ではなく、「楽しく続けられるもの」にするために、いくつかの工夫を取り入れると良いでしょう。
ここでは、すららを効果的に活用するための具体的な方法を紹介します。
使い方1・「短時間×頻度」でリズムを作る/1回20〜30分を目安に、毎日少しずつ続ける
小学生は、長時間の勉強に集中するのが難しいため、1回あたりの学習時間を短く設定することが大切です。
すららを使う際は、1回20〜30分を目安にし、「短時間でもいいから毎日続ける」ことを意識すると、学習習慣が定着しやすくなります。
例えば、「朝ごはんのあとに20分」「学校から帰ってきたら30分」といったように、日々のルーティンに組み込むと、無理なく学習を続けられます。
また、「今日は疲れているからやめる」ではなく、「疲れていても5分だけやる」など、少しでも触れる習慣を作ることで、学習が途切れることを防げます。
使い方2・「ごほうび制度」を活用する/1ユニット終わったらシールを貼るとか、小さな達成感を演出すると、やる気が続く
小学生の学習意欲を高めるには、「達成感を感じる仕組み」を作ることが重要です。
すららのユニットを1つ終えたら、シールを貼る、スタンプを押す、お気に入りのお菓子を食べるなど、子どもが「やってよかった!」と思える仕組みを取り入れると、学習のモチベーションが続きやすくなります。
例えば、「ユニットを5つクリアしたら好きな本を買う」「1週間毎日続けたら家族でゲームをする時間を作る」といったように、楽しみながら続けられる工夫をすると、勉強に対する前向きな気持ちが育ちます。
使い方3・親も一緒に楽しむ姿勢を/とくに低学年は、親が「一緒にやろう!」と言うと素直に取り組むことが多い
特に低学年の子どもは、親が一緒に勉強をすることで、学習意欲が大きく変わります。
親が「勉強しなさい」と言うのではなく、「一緒にやってみよう!」と声をかけると、子どもは自然と学習に取り組みやすくなります。
例えば、すららの問題を一緒に見ながら、「これはどう思う?」と問いかけたり、「お母さん(お父さん)もやってみようかな」と興味を持つ姿勢を見せることで、子どもも楽しく学習できます。
また、子どもが正解したときに「すごいね!」と褒めたり、間違えたときには「どこが違ったのか考えてみよう」とサポートしてあげることで、子どもは安心して学ぶことができます。
使い方4・苦手克服から入るのがおすすめ/好きな科目ばかりやると偏るから、すららのAI診断で弱点を把握して、そこから攻略する
すららでは、AIが苦手な分野を分析し、どこを重点的に学習すればよいのかを提案してくれます。
小学生は好きな科目ばかりをやりがちですが、苦手を放置すると、学年が上がるにつれて「つまずき」が大きくなってしまうことがあります。
そのため、すららを活用する際は、まずはAI診断を活用して、子どもがどこでつまずいているのかを把握し、苦手克服から始めるのがおすすめです。
例えば、「算数の計算はできるけど文章問題が苦手」「国語の漢字は覚えられるけど読解が苦手」など、細かい苦手ポイントを特定し、そこを重点的に学ぶことで、学習の効果が高まります。
すららなら、過去の学年の内容にも戻って復習できるため、理解不足の部分をしっかり補強することができます。
すららは、ただ「やらせる」のではなく、「楽しく続ける工夫」を取り入れることで、より効果的に学習を進めることができます。
特に小学生は学習習慣がまだ定着していないため、親のサポートや工夫次第で、勉強に対する意欲を大きく伸ばすことができます。
無理なく継続できる学習環境を整えて、子どもが自分から進んで学ぶ姿勢を育てていきましょう。
【中学生】すららの効果的な使い方について紹介します
中学生になると、定期テストや部活、学校行事などで忙しくなり、計画的に勉強を進めることが大切になります。
すららは、自分のペースで学習できる無学年式の教材なので、時間を上手に使いながら効率よく学ぶことができます。
ここでは、中学生がすららを効果的に活用する方法を紹介します。
使い方1・「定期テスト対策」に直結させる/単元ごとにまとめテストがあるから、テスト範囲を逆算して、今どこをやるべきか計画を立てる
定期テストで良い成績を取るためには、計画的に学習を進めることが重要です。
すららでは、各単元ごとにまとめテストが用意されているため、「テスト範囲を逆算して、今どこを重点的に学ぶべきか」を明確にしやすいのが特徴です。
例えば、テスト2週間前になったら、すららのまとめテストを活用して、「まだ理解が浅い部分」を見つけ、そこを重点的に復習すると効率よく学習を進めることができます。
また、AIが苦手な部分を分析し、必要な復習を提案してくれるため、やみくもに勉強するのではなく、「得点に直結する学習」を進めることができます。
学校のワークやプリントと併用しながら、「今やるべきこと」を明確にすると、テスト勉強の効率が大幅にアップします。
使い方2・部活後の「夜学習」を習慣に/寝る前の「タブレット学習ルーティン」を決めると、ペースが乱れない
中学生は部活や習い事で忙しく、なかなか勉強時間を確保するのが難しいこともあります。
そこでおすすめなのが、「夜の学習ルーティン」を作ることです。
すららはタブレットやPCで学習できるため、寝る前の30分だけ勉強する習慣をつけると、毎日の学習が定着しやすくなります。
例えば、「部活が終わったら30分だけすららをやる」「お風呂の後に英語のリスニングをする」といったように、生活の流れに学習を組み込むことで、無理なく続けることができます。
特に、夜寝る前に学んだ内容は記憶に残りやすいため、暗記系の科目(英単語・歴史・理科の用語など)を重点的に学ぶと効果的です。
使い方3・「すららコーチ」をフル活用/学習計画のアドバイスやつまずきのサポートをしてくれる
中学生になると、勉強が難しくなり、「どこが分からないのか自分で気づけない」「どの順番で勉強すればいいのかわからない」といった悩みを抱えることも増えてきます。
そんなときに活用したいのが、「すららコーチ」のサポートです。
すららコーチは、学習計画のアドバイスをしてくれるだけでなく、つまずいた部分をどう克服するかを一緒に考えてくれる存在です。
「勉強をやる気になれない」「どこから手をつけたらいいかわからない」と悩んでいる場合は、積極的にすららコーチに相談すると、自分に合った学習プランを立ててもらえます。
特に、定期テスト前や受験勉強を始めるときには、すららコーチのアドバイスを活用することで、勉強の効率を上げることができます。
使い方4・「復習と予習」をバランスよく/英語や数学の文法・公式の理解は予習でやると授業が楽しくなる
中学生の勉強では、「授業の内容を理解するために予習をすること」と、「習ったことを定着させるために復習をすること」の両方が大切です。
すららでは、授業の予習として使うこともできるため、特に英語や数学のような「積み重ねが必要な科目」は、事前に学習しておくと授業が理解しやすくなります。
例えば、英語の文法をすららで予習しておけば、学校の授業で「なんとなくわかる」状態になり、授業中の理解が深まります。
数学も、公式や計算の基本をすららで確認しておけば、学校の授業での演習がスムーズに進みます。
逆に、社会や理科などの暗記系科目は、すららを「復習」に活用し、テスト前にしっかり定着させると効率よく学習を進めることができます。
すららは、中学生の忙しいスケジュールに合わせて柔軟に学習できる教材です。
定期テスト対策、部活との両立、学習計画のサポートなど、うまく活用すれば学習の効率を上げることができます。
自分に合った学習スタイルを見つけ、無理なく続けることで、確実に成績アップにつなげていきましょう。
【高校生】すららの効果的な使い方について紹介します
高校生になると、勉強の内容が一気に難しくなり、大学受験や進路を意識した学習が求められます。
しかし、学校の授業についていくのが難しいと感じたり、部活やアルバイトで忙しくなったりすることで、勉強のペースが乱れてしまうこともあります。
そんなときに役立つのが、すららの「無学年式学習」と「AIによる学習サポート」です。
高校生は、目的に応じてすららを活用することで、効率よく学習を進めることができます。
ここでは、高校生におすすめのすららの使い方を紹介します。
使い方1・「苦手克服」×「得意分野の強化」を並行する/つまずいてるところは基礎から復習し、得意分野は応用問題に挑戦する
高校生の勉強では、「苦手克服」と「得意分野の強化」をバランスよく進めることが重要です。
すららは無学年式の学習システムを採用しているため、苦手な単元に戻って学び直すことができるのが大きなメリットです。
例えば、「数学の二次関数が苦手なら、中学の比例・反比例から復習する」といったように、基礎から積み上げることができます。
一方で、得意な分野については、すららの応用問題や発展問題に挑戦し、さらなるレベルアップを図ることが可能です。
このように、苦手な単元は基礎から復習しながら、得意分野はどんどん進めることで、効率的に学力を伸ばすことができます。
使い方2・学校の授業が合わない場合は、すららで自分に合うペースで進める
高校の授業は、学校や先生によって進度が異なり、自分に合わないと感じることもあります。
「授業が速すぎてついていけない」「逆に、授業が遅くてもっと先に進みたい」と思う場合、すららを活用することで、自分に合ったペースで学習を進めることができます。
特に、苦手な科目は「もう一度基礎からやり直したい」と思うことがあるかもしれませんが、学校の授業ではなかなか戻って学習する時間がありません。
すららなら、理解が不十分な部分をさかのぼって学習できるため、着実に知識を定着させることができます。
また、学校の授業よりも早いペースで学習したい場合も、すららなら自由に先取り学習が可能です。
例えば、「数学は授業よりも先に進めておいて、学校の授業を復習として活用する」といった学習方法も効果的です。
学校のペースにとらわれず、自分に最適な学習スピードを選べるのが、すららの大きな強みです。
使い方3・模試や共通テスト対策に連動/すららは基礎力の定着にはかなり強い
高校生になると、模試や共通テスト対策を意識した学習が必要になります。
すららは、基礎をしっかり固めるのに適しているため、模試や大学受験の対策にも活用できます。
特に、共通テストでは「知識を正確に理解し、素早く解く力」が求められるため、すららで基礎をしっかり身につけることで、応用問題にも対応しやすくなります。
模試を受けた後は、「間違えた部分をすららで復習する」ことで、苦手分野を克服しやすくなります。
例えば、数学の関数の問題が苦手なら、すららの講義で基本的な概念を確認し、演習問題を解きながら理解を深めることができます。
このように、「模試の結果を分析→すららで復習→次の模試で改善」といったサイクルを作ることで、学力の向上につなげることができます。
使い方4・学習時間を「見える化」する/学習時間や達成度がグラフで表示される
すららでは、自分がどれくらい学習したのかを「見える化」できるシステムが搭載されています。
学習時間や達成度がグラフで表示されるため、「今日は○時間勉強した」「今月は○○単元をクリアした」といった進捗を把握しやすくなります。
特に、高校生は学習時間を確保するのが難しくなりがちですが、学習の記録を可視化することで、モチベーションを維持しやすくなります。
また、学習の進捗を振り返ることで、「この科目に時間をかけすぎている」「もっと英語の学習時間を増やしたほうがいい」といった改善点も見つけやすくなります。
学習計画を立てる際にも、「週に何時間勉強するか」「どの科目に重点を置くか」を明確にできるため、効率的に学習を進めることができます。
高校生がすららを活用する際は、「苦手克服と得意強化のバランス」「自分のペースで進める」「模試対策への活用」「学習の見える化」といったポイントを意識することで、より効果的に学習を進めることができます。
大学受験に向けて、基礎力をしっかり固めながら、すららを最大限に活用していきましょう。
【不登校】すららの効果的な使い方について紹介します
不登校の子どもにとって、学習の継続はもちろん、生活リズムの維持や自己肯定感の回復が大きな課題となります。
学校に通えない期間が長くなると、学習の遅れや「自分だけが取り残されているのでは?」という不安を感じることもあるかもしれません。
すららは、不登校の子どもが自宅で無理なく学習を続けられるように設計されており、生活のリズムを整えたり、自信を取り戻したりするのにも役立ちます。
ここでは、不登校の子どもがすららを効果的に活用する方法を紹介します。
使い方1・「生活リズム作り」に役立てる/朝起きる→学習→休憩…の「ミニ時間割」を作って生活リズムを整えられる
不登校の期間が長くなると、昼夜逆転してしまったり、ダラダラと過ごしてしまったりすることが増えることがあります。
しかし、生活リズムが乱れると、気持ちの面でも不安定になりやすく、学習の意欲も低下しがちです。
すららを活用することで、「朝起きる→学習する→休憩する」といったシンプルなミニ時間割を作り、規則正しい生活を送るサポートができます。
例えば、「朝9時に起きたら30分だけすららをやる」「午後3時に1ユニットだけ進める」といった小さな習慣を作ることで、無理なく学習を生活の一部に取り入れることができます。
最初から長時間勉強しようとすると負担になることもあるため、「短時間×継続」を意識するのがポイントです。
使い方2・「一人でも安心してできる環境」を整える/自分のペースで、周りを気にせず学べるのがすららの強み
不登校の子どもにとって、「学校のペースに合わせなければならない」というプレッシャーは大きな負担になります。
すららは無学年式の学習システムを採用しているため、学校の進度を気にせず、自分のペースで学習を進めることができます。
また、学校のように周囲の目を気にすることがなく、自宅でリラックスしながら学べるのも大きなメリットです。
「クラスメイトと比べられるのが嫌だ」「授業中に当てられるのが怖い」という気持ちがある場合でも、すららなら安心して学習に集中できます。
自分の理解度に合わせて学べるため、「分からないまま置いていかれる」ことがなく、少しずつ着実に学力を取り戻すことができます。
使い方3・「成功体験」を増やして自信を回復/すららの「ほめ機能」を活用する
不登校の子どもは、「勉強が遅れてしまった」「学校に行けない自分はダメなのでは」と自己肯定感が下がってしまうことがよくあります。
すららでは、学習を進めるごとに「できた!」という達成感を感じられる工夫がされており、小さな成功体験を積み重ねることで、自信を回復することができます。
例えば、すららの授業はアニメーション形式で進むため、分かりやすく、理解しやすい作りになっています。
さらに、「問題に正解するとキャラクターがほめてくれる」といった機能もあり、「頑張ったことを認めてもらえる」体験を積み重ねることができます。
勉強が苦手な子でも、「1ユニット終わった!」「今日は5問正解できた!」といった小さな成功を感じることで、「もっとやってみよう」という前向きな気持ちになりやすくなります。
使い方4・コーチングの活用で「孤立感」を減らす/すららコーチに相談すると、親とは違う「第三者の声」がもらえるので、気持ちの負担が和らぐ
不登校の子どもは、学習だけでなく「社会とのつながりが少なくなる」ことに不安を感じることがあります。
親がサポートしていても、「親だからこそ言いにくいことがある」「親に心配をかけたくない」といった気持ちから、気持ちを話しづらくなることもあるでしょう。
すららには、「すららコーチ」と呼ばれる学習サポートスタッフがいて、学習の進め方や悩みについて相談することができます。
すららコーチは、発達障害や不登校の子どもに対する対応経験があることが多く、一人ひとりの状況に寄り添いながらアドバイスをしてくれます。
「どうやって勉強を進めればいいか分からない」「やる気が出ない」といった相談にも乗ってくれるため、孤立感を減らしながら学習を続けることができます。
また、親が学習を管理するのではなく、すららコーチが学習計画を提案してくれるため、親子の関係も良好に保ちやすくなります。
「親に言われるとやる気がなくなるけど、第三者から言われるとやる気が出る」というケースも多いため、すららコーチを上手に活用することで、無理なく学習を進められる環境を作ることができます。
すららは、「生活リズムの維持」「一人でも安心して学べる環境」「成功体験の積み重ね」「第三者のサポート」という4つのポイントを活かして、不登校の子どもが無理なく学習を続けられるように設計されています。
「学校に行けない間の勉強が不安」「自信を取り戻したい」という場合は、すららを活用して、少しずつ学習のペースを整えていくのがおすすめです。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららを実際に利用したユーザーの評判を紹介します
良い口コミ1・うちの子は、元々タブレットが好きで、ゲーム感覚で学べるところがハマったみたいです。アニメのキャラが優しく教えてくれるので、塾に行くよりも緊張しないし、自分のペースでできるのが良いみたい
良い口コミ2・ADHD気味で集中力が長続きしない子でも、すららはアニメーションやイラストで説明してくれるので理解しやすいです
良い口コミ3・学校に通えない期間が長く、勉強にブランクがありましたが、すららなら自分のレベルに合わせて無理なく進められました。先生の顔を見ずに自分だけのペースで学べるので、安心感があります
良い口コミ4・塾に通う時間が取れなかったけど、すららは家でスキマ時間にできるから便利!部活が忙しくても、夜に少しずつ進めていけるし、テスト対策にも使えるのがいい
良い口コミ5・発達に凸凹があって、書くことが苦手な子ですが、すららはタブレット操作で進められるので、嫌がらずに学習ができています
悪い口コミ1・タブレットで勝手に学んでくれると思っていたけど、低学年の子は一人で進めるのが難しいこともあり、結局そばで見守ることに…。もう少し親が楽できる設計だったらよかったかな
悪い口コミ2・初めは楽しく続けられていたのですが、不登校の子だと一度やる気が下がると放置してしまう…。サポートメールや先生からのアドバイスは来るけど、やっぱり一人だと限界を感じることもあります
悪い口コミ3・高校生用のコースを受講していますが、基礎に時間をかけすぎる印象です。進学校に通っていると、物足りなさを感じるかもしれません
悪い口コミ4・アニメーションで楽しく学べるのはいいけれど、うちの子は飽きるのも早くて…。もう少し、変化に富んだコンテンツがあると良いですね
悪い口コミ5・通塾よりは安いですが、長期間利用を考えるとそれなりに負担感があります。特に兄弟で同時に使う場合は、一人ずつの契約が必要なので、コストはやっぱりかさみます

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの会社概要を紹介します
| 運営会社 | 株式会社すららネット |
| 創業 | 2008(平成20)年8月29日 |
| 本社住所 | 〒101-0047
東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田7階 |
| 従業員数 | 正社員88人、契約社員5人 |
| 資本金 | 298,370千円 |
| 代表取締役 | 湯野川 孝彦 |
| すらら公式サイト | https://surala.co.jp/ |
| すららの講座一覧 | ・3教科(国・数・英)コース
・4教科(国・数・理・社)コース ・5教科(国・数・理・社)コース |
参照: 会社概要 (すらら公式サイト)

【すらら】はうざい!?についてのよくある質問
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
「すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?」という意見に対して、実際の理由は様々な要因が絡んでいます。
一般的に、人々が「うざい」と感じる原因には、サービスの提供方法やコンテンツの質、またはユーザーの期待に対する満足度の不一致などが挙げられます。
さらに、個々の感情や経験によっても評価は異なるため、単純に「うざい」と言われるだけでその理由が一概には言えません。
ただし、ユーザーからの批判はそのサービスに潜む問題を把握する上で重要な指標となります。
これを機会と捉え、改善点を見つけ出し、ユーザー満足度向上に努めることが重要です。
皆様の貴重なご意見を真摯に受け止め、より良いサービスの提供に努めてまいります。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららの発達障害コースの料金プランについてお聞きします。
すららでは、発達障害を抱える方々に向けた専門的なサービスを提供しており、その料金プランについて詳細にご案内いたします。
まず、当コースの料金設定は、個々のニーズや状況に合わせて柔軟に対応しております。
そのため、一律の料金表記はございません。
発達障害コースでは、専門のカウンセラーや教育専門家による指導やサポートが含まれており、その内容に応じて料金が設定されます。
お気軽にお問い合わせいただければ、お客様お一人おひとりに最適なプランをご提案させていただきます。
お問い合わせやご相談については、いつでもお気軽にお寄せくださいませ。
関連ページ: すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
多くの親が気になる質問の一つである、「すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?」について、詳しくお伝えいたします。
不登校の子供における出席扱いに関しては、すららのタブレット学習は一般的な登校と同様になるわけではありません。
多くの学校が出席を認める際には、学校側が提供する指定の学習教材やテキストに基づく場合が一般的です。
したがって、すららのタブレット学習が学校側での出席扱いになるかどうかは、その学校の方針や規定によって異なります。
ただし、すららのタブレット学習は柔軟性があり、個別の学習スタイルやペースに合わせて進めることができるため、不登校の子供の教育支援には有効なツールとして活用されることがあります。
保護者や学校との相談の上、適切な形で活用することで、不登校の子供にとって良い学習環境を整える手助けとなるでしょう。
したがって、すららのタブレット学習は不登校の子供にとって有益な教育支援の一つとして捉えることができます。
最終的な出席扱いについては、学校や教育機関との相談を通じて検討することが重要です。
不登校の子供に対する個別の配慮やサポートを考慮しながら、最良の教育環境を構築するための一環として、すららのタブレット学習の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
関連ページ: すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららのキャンペーンコードを活用してサービスを提供するための手順について詳しく説明いたします。
初めに、すららのウェブサイトにアクセスして、ご希望のサービスを選択してください。
その際、支払いページでキャンペーンコード入力欄がございますので、そちらにご利用いただけるコードを入力してください。
その後、値引きや特典などの適用が確認されるかと思います。
該当する場合、割引が適用された金額が表示されます。
是非この機会にお得にすららのサービスをご利用ください。
どうぞお楽しみください。
関連ページ: すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
当社のサービス「すらら」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
お客様が「すらら」を退会されたいということを理解いたしました。
退会手続きについてお知らせいたします。
まず、「すらら」の退会手続きを行うには、以下の方法があります。
当サービスへのアクセス後、マイページにログインしていただきます。
そこで、退会手続きが可能な画面をご案内いたします。
必要事項を入力いただき、手続きを完了させていただきます。
退会手続きが終了いたしましたら、登録情報は全て削除されますので、何卒ご了承ください。
もし再度「すらら」をご利用いただく際には、再度新規登録が必要となりますので、ご注意ください。
退会に関するご不明点やご質問がございましたら、お気軽に弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。
お手続きや情報提供にお手伝いいたします。
お客様のご利用、誠にありがとうございました。
今後のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
関連ページ: すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららを利用する際にかかる費用は、基本的に「入会金」と「毎月の受講料」のみです。
入会金は一度だけ発生し、その後は月額の受講料を支払うことで学習を継続できます。
追加の教材費や設備費などは不要なので、シンプルな料金体系となっています。
ただし、すららを利用するための「タブレットやPC、インターネット環境」は別途必要になります。
また、一部の支払い方法によっては、振込手数料がかかる場合があるため、申し込み時に確認すると安心です。
また、コース変更や科目追加を希望する場合は、追加料金が発生することもあるので、詳細は公式サイトやサポートセンターに問い合わせるとよいでしょう。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららでは、1つの契約で兄弟・姉妹が一緒に利用することが可能です。
つまり、1人分の受講料を支払えば、同じアカウントを共有して複数人で学習することができます。
ただし、1つのアカウントを共有するため、それぞれの学習進捗や成績が個別に記録されるわけではありません。
兄弟それぞれの学習履歴をしっかり管理したい場合は、別々にアカウントを作成することも検討するとよいでしょう。
また、学年が大きく離れている場合でも、すららの無学年式システムを活用すれば、兄弟それぞれのレベルに合わせた学習が可能です。
特に「上の子と一緒に下の子も勉強させたい」「兄弟で協力しながら学習したい」と考えている家庭には、とてもコスパの良い選択肢となります。
すららの小学生コースには英語はありますか?
すららの小学生コースには、国語・算数・理科・社会の4教科に加えて、「英語」も含まれています。
小学校の英語は、「リスニング」「スピーキング」「リーディング」に対応しており、ネイティブの発音を聞きながら学習することができます。
特に、小学生のうちから英語に親しむことは、中学以降の英語学習にとって大きなメリットになります。
すららの英語コースでは、アニメーションを活用した対話型の授業が特徴で、遊び感覚で英語に触れながら学習できるのが魅力です。
また、発音練習機能も備わっているため、「聞く」「話す」力を伸ばすのに最適です。
英検対策にも役立つ内容が含まれているため、英語を本格的に学びたい小学生にもおすすめです。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららでは、学習をサポートする「すららコーチ」がついており、学習の進め方やモチベーション管理についてサポートを受けることができます。
すららコーチのサポート内容は以下のようなものがあります。
1. **学習計画の作成**
– 子どもの学習状況や理解度に合わせたスケジュールを作成してくれる
– どの単元をどの順番で学習すればよいかをアドバイス
2. **学習の進捗管理・モチベーションサポート**
– 定期的に学習の進み具合をチェックし、必要なサポートを提供
– 「やる気が出ない」「続かない」といった悩みに対して、適切な声かけやアドバイスをしてくれる
3. **つまずきのフォロー**
– 「どこでつまずいているのか」を分析し、復習すべき単元を提案
– つまずいた部分の解説や、効果的な学習方法をアドバイス
4. **保護者へのサポート**
– 保護者と連携しながら、子どもの学習状況を共有
– 学習に関する相談に対応し、子どもに合った学習スタイルを提案
すららコーチのサポートを活用することで、親が細かく学習管理をしなくても、子どもが自分のペースで無理なく学習を進めることができます。
また、「第三者からのアドバイス」を受けることで、親子間の学習に関するストレスも軽減されるメリットがあります。
特に、不登校や発達障害のあるお子さんの場合、「勉強の仕方がわからない」「やる気が出ない」といった悩みを抱えやすいため、すららコーチのサポートを上手に活用することで、安心して学習を進めることができます。
参照: よくある質問 (すらら公式サイト)

【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材と比較しました
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |

【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較まとめ
以上、【すらら】に関する料金や最悪の噂、口コミなどを比較してまとめてきました。
お子様の教育においてタブレット教材を検討されている保護者の皆様にとって、本記事が参考になれば幸いです。
【すらら】は様々な意見や評価がありますが、その中から自身のニーズに合った教材を選ぶことが重要です。
料金面や機能面だけでなく、お子様の学習スタイルや興味に合った教材を選ぶことが、学習効果を最大化するポイントとなります。
また、口コミや評判を参考にする際には、複数の情報源を総合的に判断することが大切です。
最終的には、お子様の成長や学習をサポートする視点で選択することが重要です。
【すらら】を含むタブレット教材を活用することで、お子様の学習環境を豊かにすることができるかもしれません。
しかし、一方で過剰な依存や負の影響を招く可能性もあることを忘れずに、適切な管理とバランスを保つことも大切です。
保護者の皆様がお子様の成長を見守りながら、最適な学習環境を整えることを願っています。

